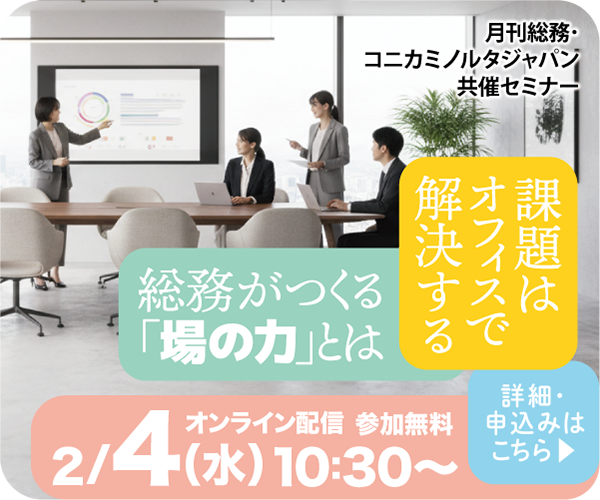平成終了まであと少し 改元対応のポイント
アクセスランキング
2019年4月30日をもって、30年続いた「平成」が終わりを迎えます。
新元号「令和」の発表で盛り上がる昨今、改元に伴う混乱はまだまだ続きそうですが、企業活動においては具体的にどのような影響が出るのでしょうか。改元のタイミングがわかっているのが今までとは異なる点。残りの時間で何をすべきか、何に注意すべきか、業務を滞りなく行うためにも、対応のポイントを確認していきましょう。
法務の視点から見る改元とは
「元号」と「改元」

1987年司法試験合格、1990年4月弁護士登録(東京弁護士会)主要著書:『Q&Aよくわかる高齢者への投資勧誘・販売ルール』『金融機関コンプライアンス・オフィサーQ&A』『アパートローンのリスク管理』共著(金融財政事情研究会)
元号とは、「年に付ける呼び名」(大辞林参照)を意味します。特に、中国において漢の武帝の時代に「建元」と称したものを最古として、わが国では645年の「大化」が初めての元号とされました。30年前に昭和から平成に改元されたことを覚えている方も多いと思います。
現代日本の元号は、「元号法」を根拠としています。この法律はとても短い法律で、「元号は、政令で定める」「元号は、皇位の継承があった場合に限り改める」という2つの項から構成されています。
改元は、元号を改めることを意味しますが、元号法の2項によれば、皇位の継承に伴って改元されます。つまり、皇位継承に際して、内閣が新しい元号を定めた政令が施行されたときから改元されることとなります。
天皇の退位等に関する皇室典範特例法の概要
ところで、2017年6月16日に「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」(以下、「皇室典範特例法」)が公布されたことをご存じでしょうか。
「皇室典範」とは、皇位継承等皇室に関する事項を規定した法律です。皇室典範第四条には、「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」とありますから、原則として天皇崩御に伴って改元されることになります。
しかし、今上天皇陛下が生前退位について、強いお気持ちをお示しになられたことから、皇室典範特例法が制定されました。皇室典範特例法第一条では、同法の趣旨を次のように述べています。
「天皇陛下が、昭和64年1月7日の御即位以来28年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励してこられた中、83歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに、皇嗣である皇太子殿下は、57歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範第四条の規定の特例として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとする」
皇室典範特例法は、「天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する」と定め、退位した天皇を「上皇」とし、上皇の后を「上皇后」としています。 さらに、皇位継承に伴い、皇嗣となった皇族については、皇室典範に定める事項について皇太子の例によるとしています。
では、改元は企業法務にどのような影響を与えるのでしょうか。
企業法務への影響は
改元されると、それ以後、古い元号を使用しなくなります。しかし、国や地方公共団体では、年号を元号で表記することが一般的であり、法律上も記載されているものもあります。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。