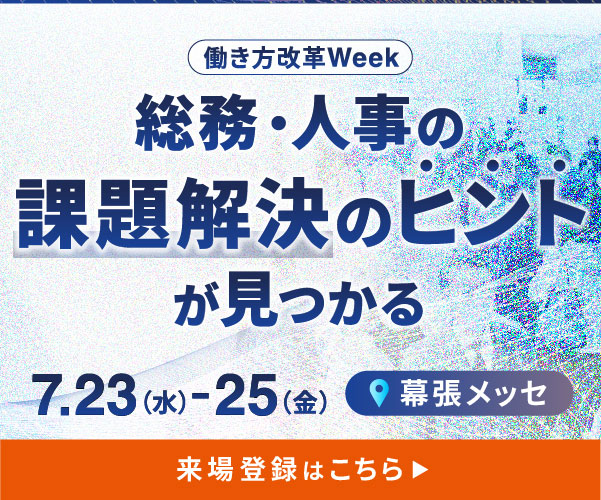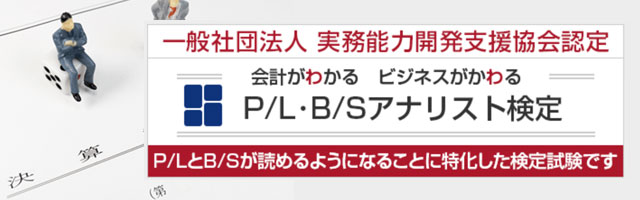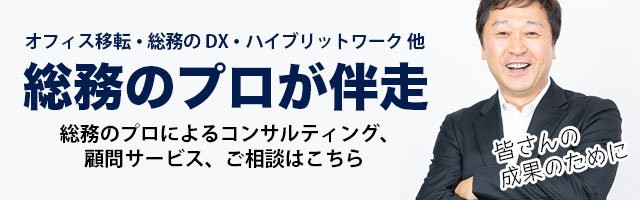大規模調査×銀行データが明かす副業のリアル 職種別に見る「働き方」とその目的
月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2025年06月30日

アクセスランキング
「副業」が一般化する一方で、その実態は一様ではない。生活費を補うためのギグワークもあれば、スキルを活かしてキャリア形成を目指す副業もある。では、こうした働き方は職種によってどう異なるのか。銀行データと8800人規模の調査から、副業の「向き・不向き」の構造が浮かび上がってきた。
ひとつは早稲田大学(東京都新宿区)とみずほ銀行(東京都千代田区)の共同研究による実証分析。もうひとつは、パーソルイノベーション(東京都港区)が発表した定点観測調査である。
フードデリバリー型ギグワークは、生活防衛の「緩衝材」
早稲田大学教育・総合科学学術院の黒田祥子教授と大西宏一郎教授の研究チームは6月27日、匿名化された銀行口座データを活用し、フードデリバリー型ギグワーカーの実態を実証的に分析した結果を明らかにした。調査期間は2016年から2021年におよび、預金残高やギグ就業履歴などを時系列で解析したものである。
分析の結果、フードデリバリー型のギグワーカーは若年層・男性・低流動性層が主流であり、就業直前には預金残高が徐々に減少していた傾向が確認された。とくにコロナ以前では、ギグワーク開始時に預金残高が10万円未満だった人は、全体の7割を超えていた。
さらに、コロナ禍では中高年や女性、比較的資金に余裕のある層も新たに参入し、就業層の多様化が進んだことも判明した。開始後1か月での離脱率が3、4割に達することからも、ギグワークが「短期的な所得補てん」の役割を果たしていることがうかがえる。
本研究は、早稲田大学とみずほ銀行が締結する共同研究契約に基づく取り組みで、金融データを通じた労働供給行動の可視化は、景気や家計資金の変動と就業選択の関係を捉える上で貴重な知見といえる。
職種によって異なる副業の実態
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。