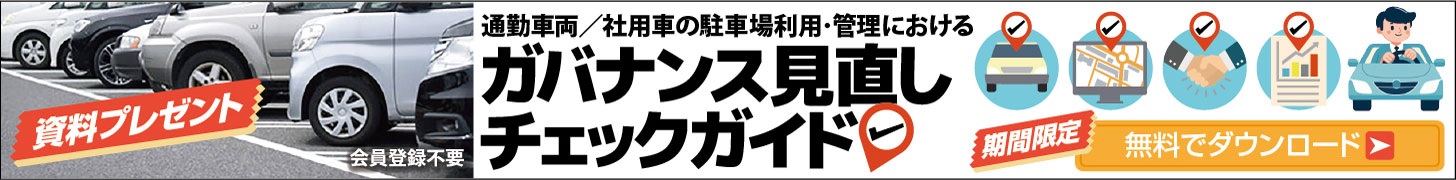2024年4月から義務化、障がい者への「合理的配慮」とは? 当事者の職場での困りごとを紹介
月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2023年07月31日

アクセスランキング
ミライロ(大阪府大阪市)が事務局を務める「民間事業者による合理的配慮提供の推進委員会」は7月28日、約2000人の障がい者を対象とした実態調査の最新レポートを公開した。改正障害者差別解消法の施行が2024年4月1日と決定している中で、障がい当事者が求める合理的配慮をまとめたもの。
今回のレポートでは、職場で当事者がどのようなことに困ったかなどを調査・分析している。
仕事や職場、4割が「合理的配慮が不十分」と感じる
障がいのある人(N=2362)に、日常生活のどのような場面で「合理的配慮が不十分だと感じるか」を聞いたところ、「仕事や職場」(950人)が最多となった。次いで、「公共交通機関」(861人)、「日常のお買い物や飲食などのサービス提供時」(685人)と続いた。
一方、全体の25%は「不十分と感じたことがない」(489人)と回答した。
合理的配慮の提供が不十分だと感じても、大半の人は「あきらめている」
また、合理的配慮の提供が不十分だと感じたとき、どのようなアクションをとるかを聞いたところ、「何もしない」(736人)という回答が最も多く、「あきらめている」というコメントが多数を占めた。
行動を起こしたという回答の上位は、以下の通りだった。
- 「その場で指摘し対応を求める」(317人)
- 「事業者に問い合わせて改善を求める」(306人)
- 行政窓口に相談する(261人)
- SNS、ネットに投稿する(150人)
当事者はどんなことに困っている?具体的な声
同調査では、当事者が具体的にどのような経験をしたかの声を掲載している。
仕事や職場での苦労
- 突発的な体調不良や障がい悪化に対する理解が薄く、自己管理不足として認識された(30歳代・精神障がい)
- 体質的にトイレが近いので複数回行っていたら、サボっていると怒られた(30歳代・内部障がい)
- 拡大文字の必要性を理解されず、対応してもらえなかった(50歳代・視覚障がい)
公共交通機関利用時の苦労
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。