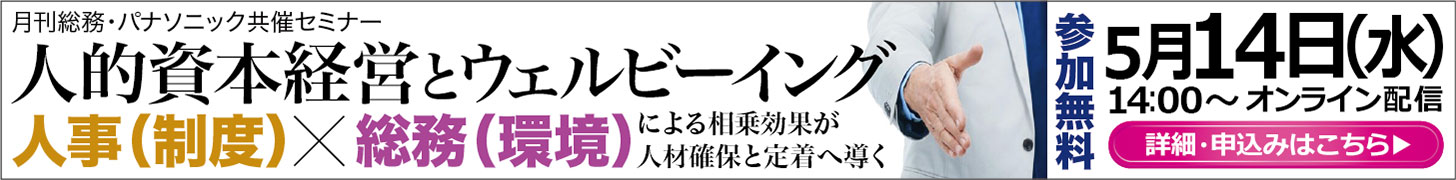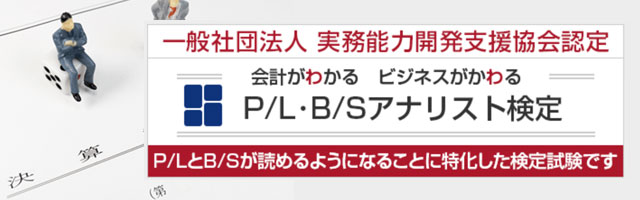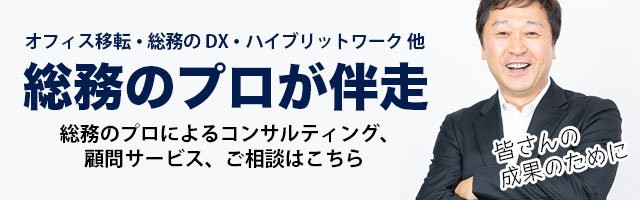4月から始まった「改正育児・介護休業法」 制度についての基礎知識をおさらい

アクセスランキング
育児・介護休業法の目的は、子の養育や家族の介護を容易にするために事業主が働き方などの制度を準備することで支援し、雇用継続をはかり、働く人が仕事と家庭の両立支援を 受けることで結果的に経済・社会の発展に役立つことと定められています。両立支援制度は、主に育児や介護による休業の制度と、休業ではなく仕事との両立を実現するための制度の2つに区分することができます。主な制度について確認していきましょう。
育児休業制度
女性従業員が妊娠・出産する際に仕事を休むことができる制度は労働基準法に定めのある産前産後休業で整備されています。
産後56日の産後休業のあとは、子を養育するために仕事を一時的に休める制度として、育児・介護休業法に定めのある育児休業制度があります。
育児休業は男女いずれでも取得可能な制度で、子の養育を行う労働者の雇用の継続や職業生活と家庭生活との両立を支援する制度として休業だけではなく、所定労働時間の短縮などの一定の制限の中で継続雇用できるように考えられている両立支援の制度もあります(休業以外の制度については後述)。
休業できる期間
育児休業制度は、原則子が1歳になるまで休業できる制度です。しかし1歳になるタイミングで保育園に入園できないなどの事情に該当すれば、1歳半まで、さらに1歳半のタイミングでも同様の事情に該当すれば2歳まで延長できます。
また、特例として労働者の配偶者も1歳より前に育児休業を取得している場合は、保育園に入園できないなどの事情がなくても1歳2か月まで延長可能という制度もあります(パパ・ママ育休プラス)。
出生時育児休業(産後パパ育休)
育児休業制度にはこのほかに、2022年の法改正により創設された「出生時育児休業」があります。「産後パパ育休」ともいわれており、子の出生後8週間以内に4週間まで取得できるもので、出産した女性の産後休業期間中に配偶者が育児休業を取得することを想定しています。
この出生時育児休業は2回まで分割取得することも可能です。育児休業と異なるのは、労使協定の締結により労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能という点です。
出生時育児休業は男性の育児休業促進が目的で創設されました。改正の背景には、特に出生直後の時期の柔軟な育児休業の枠組みが必要と考えられていたということがあります。
内閣府の資料によると、国立研究開発法人国立成育医療研究センターによる研究分析結果から、乳児期において父親の育児へのかかわりが多いことが、子供が16歳時点でのメンタルヘルス不調を予防する可能性が示唆されています。そのため、父親が育児休業を取得しやすくなるように環境整備することは、母親の負担を減らすことだけではなく、子にも好影響が見込まれるとも考えられているようです。
こうした出生時育児休業の創設により、育児休業期間に就労することも可能となったという点も大きな改正点と考えられます。従前は育児休業という休業の期間に就労を認めるという規定はありませんでしたが、出生時育児休業では、労働者が希望すればその休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分を上限に就労可能となります。
ただし、あくまでも労働者が希望し、その範囲で会社が決定した日時についてのみが対象となり、労働者の同意により就労可能となる仕組みです。
つまり、会社が一方的に働くことを指示できない制度であり、また本人の希望の範囲ではあるものの最終的に働く日は会社が決定する流れとなります。
育児休業も、出生時育児休業も、入社1年未満の人などを取得可能な労働者から除外することが労使協定の締結により可能です。
介護休業制度
介護休業制度とは、労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するための休業です。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。