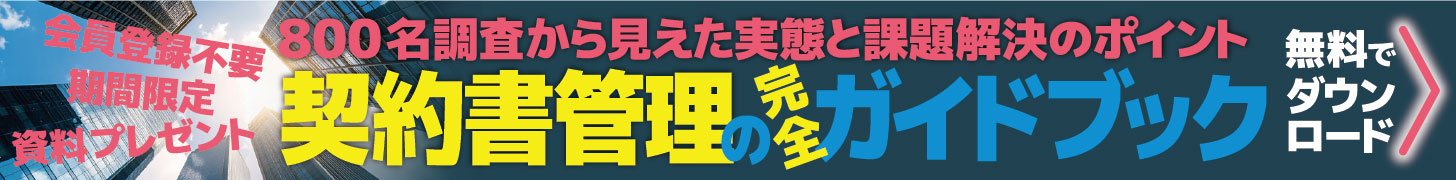それ、本当に「いいがかり」? 対策を整備する前に決めておきたい自社における「カスハラ」の定義

アクセスランキング
2022年2月に厚生労働省から「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(以下、厚労省カスハラマニュアル)が公表されました。これは、昨今、社会問題化している「カスタマーハラスメント」(以下、カスハラ)の増加、そして、それによるさまざまな現場で働く企業の従業員や関係者(医療・福祉の現場、行政機関職員など)の被害の深刻化を受けて、いよいよ国が本腰を入れて対策に取り組み出したことを意味します。
2023年に入り旅館業法も改正され、これまで宿泊客の理不尽な行為に対して強気に対応できなかった宿泊施設もカスハラを行う顧客への宿泊拒否が可能となるなど、徐々にカスハラ被害防止に向けた社会環境も整備されつつあります。このような社会の流れのほか、過去にカスハラを巡る企業側の対応に関してカスハラによる安全配慮義務違反を争われた裁判例もあり(厚労省カスハラマニュアルP.17で紹介)、今後、企業としても、カスハラから従業員を守るための対策や体制整備が必須になってきます。そこで本企画では、企業が整備すべきカスハラ対策や体制のポイントなどについて、4回にわたって解説していきます。
カスハラ対策の前にCS対応を見直そう
実際の企業におけるお客さま対応の現場を見てみると、「お客さまが怒っている」「お客さまが大声を出している」「感情的になっているお客さまが担当者に暴言を吐いた」などの一事を取り上げて、従業員がカスハラに当たるのではないかと指摘しているケースも少なくありません。しかし、このようなケースの全てがカスハラに当たるわけではありません。
最近の傾向として、企業側が当たり前のカスタマーサポート(以下、CS)対応すらできずに(せずに)、お客さまを怒らせ、クレームをこじらせているケースも散見されます。まずは謝罪から入るべきところを、言いわけから入って、火に油を注いでしまい、お客さまをエスカレートさせてしまっているケースも少なくありません。また、適切な説明・案内すらせずに、お客さまから何度も指摘されているケースも散見されます。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。