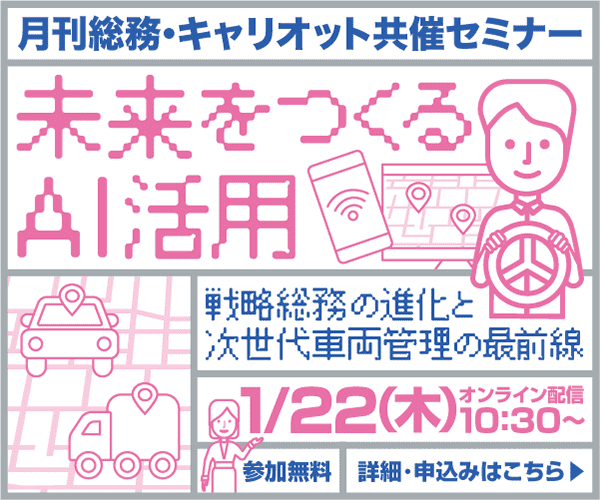アクセスランキング
猛暑の中、外回りを続ける営業職にとって、熱中症はもはや他人ごとではありません。気温と湿度が高まる真夏には、わずかな判断の遅れが、命にかかわるリスクにつながります。とはいえ、「何をどこまで備えればいいのかわからない」「うちは一人総務で限界……」という声が多いのが現実です。そこで本記事では、産業医の大室正志さんにお聞きした社外で仕事に従事する外勤の働き方に関する見解や、現場で進む最新の取り組みを基に「営業・外勤の人たちを守るために最低限やっておきたいこと」を5つの視点で整理。社員一人ひとりが自分ごととして動けるようになるための、今日から使えるヒントをお届けします。
猛暑の外勤、他人ごとではいられない理由
2025年6月1日に労働環境の安全や衛生などの確保を目的とした省令「改正労働安全衛生規則 」が施行され、職場での熱中症対策が「義務化」されました。改正により、WBGT(暑さ指数)28℃以上、もしくは気温31℃以上の環境下で1時間以上、または1日4時間超の作業を行う全ての職場で、熱中症対策の体制の整備やマニュアル作成、社員への周知が事業者に義務付けられています。
この背景には、年々深刻化する熱中症リスクがあります。実際、2010年には年間1731人が熱中症で亡くなっており、2018年はそれに次ぐ1581人が死亡。近年でも依然として深刻な被害が出ていることがわかります。2024年の交通事故死者数は2600人台 であることを踏まえると、「外回りで命を落とす」リスクは、交通事故のレベルに近づいているといえます。
それでもなお、「熱中症は高齢者や工場作業の話」「若い営業職には関係ない」と考える方も少なくありません。ですが、今やこれは誰にでも起こり得る労災リスク。外回りの営業や現場職にとっても、地球温暖化が進む今、熱中症は避けては通れない現実の脅威となっています。
事業者だけでなく、現場で働く一人ひとりにとっても、「備える責任」と「守られる権利」の両方が問われる時代が、すでに始まっているのです。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。