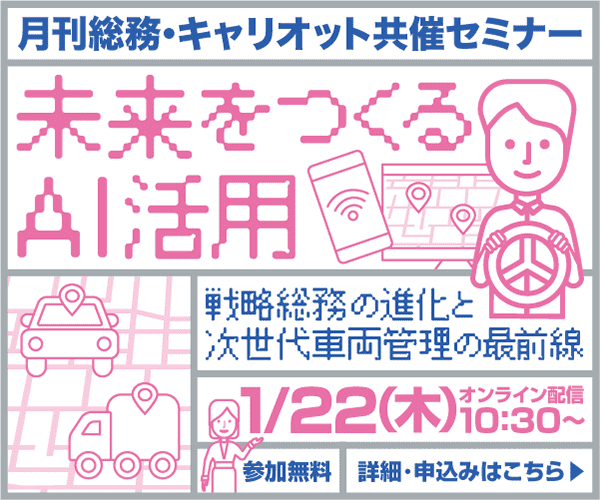厚労省で裁量労働制をめぐる議論が活発化 労使で意見が分かれる中、今後の制度設計見直しに注目
月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2025年09月05日

アクセスランキング
厚生労働省の労働政策審議会・労働条件分科会が9月4日に開催され、労働基準法の見直しに向けた議論が行われた。同会では、裁量労働制をめぐって労働者側と使用者側の意見の違いがあらためて示され、今後の制度設計に向けた論点が整理された。
裁量労働制とは 2種類の制度と適用の実態
裁量労働制とは、業務の遂行方法や時間配分などを労働者の裁量に委ねる働き方のこと。この制度では、実際に働いた時間ではなく、あらかじめ定められた一定の時間働いたものとみなして(みなし労働時間)、賃金や労働時間を管理する。
この制度には「専門業務型」と「企画業務型」の2種類がある。
専門業務型裁量労働制
厚生労働省令および告示で定められた専門的な業務に従事する労働者が対象となる。たとえば、研究開発、人文・自然科学の研究、新聞記者、コピーライター、情報処理システムの設計、銀行・証券会社におけるM&Aアドバイザリー業務などが含まれる。
適用労働者の割合は全体の1.4%、導入企業の割合は2.2%にとどまっている。
企画業務型裁量労働制
企業の経営企画や財務分析など、事業運営に関する企画・立案・調査・分析業務に従事する労働者が対象である。たとえば、経営計画や財務計画の策定にかかわる職種などが該当する。
適用労働者の割合は0.2%、導入企業の割合は1.0%と、さらに限定的な制度となっている。
裁量労働制は、労働時間の柔軟な運用を目的とした制度の一つとして設けられているが、対象や適用には明確な要件がある。そのため、制度の詳細が十分に理解されていない場合もある。
裁量労働制は2024年に見直し 対象業務の追加や健康確保措置の強化
また、2024年4月には裁量労働制に関する制度改正が施行された。主な見直し内容は以下の通りである。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。