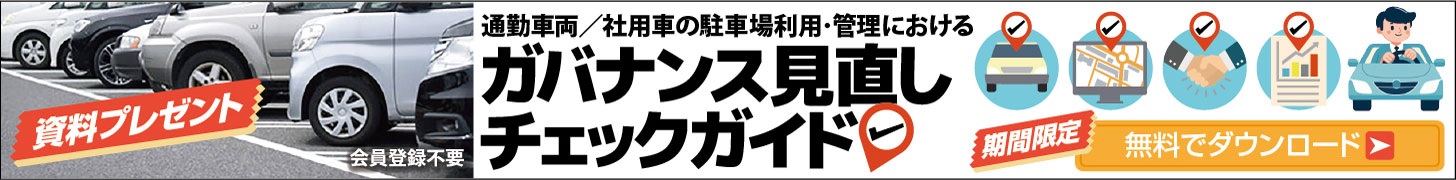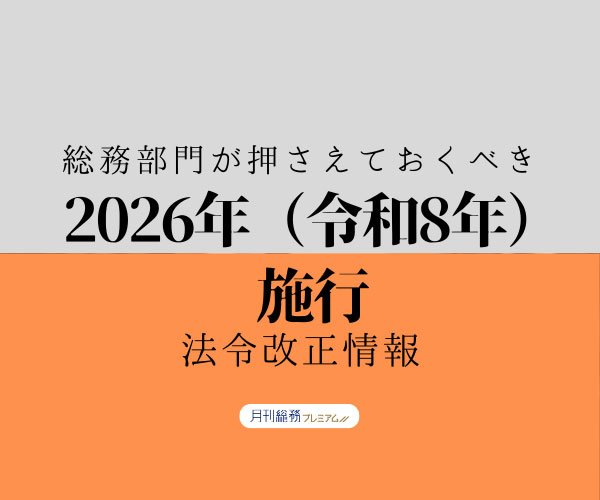パワーハラスメントは上司→部下とは限らない! 能力が高い部下などによる「逆パワハラ」3事例

アクセスランキング
企業等における危機管理を専門とする株式会社エス・ピー・ネットワークの研究員が、「HR(ヒューマンリソース)リスクマネジメント」の観点から職場のハラスメントについて解説していく本連載。今回は、部下から上司に対する「パワーハラスメント」(以下、パワハラ)について、取り上げます。
パワハラの定義と判断基準
パワハラというと、上司が部下に対し、叱責 など問題のある言動をしている場面を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。こんな固定観念を覆すようなアンケート結果があります。株式会社ジェイフィールが2025年に実施した「人・組織・コミュニティアンケート第5回 ~逆パワハラ調査~」では、課長職のうち約4割が部下からのパワハラ(逆パワハラ)を受けたことがあると回答しており、部下からのパワハラも発生しているようすがうかがえます。
本稿では部下から上司へのパワハラ事例と、パワハラ防止の取り組みについて紹介します。パワハラの定義は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)」で「職場において行われる(1)優越的な関係を背景とした言動であって、(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、(3)労働者の就業環境が害されるもの」と定義されており、(1)から(3)までの3つの要素を全て満たすものをいいます。なお、客観的に見て業務上必要かつ相当な範囲で行われる、適正な業務指示や指導については該当しないとされています。
「(1)優越的な関係を背景とした」とは、行為を受ける労働者(被害者)が、行為者(加害者)に対して抵抗や拒絶をしにくい関係とされています。上司から部下など職務上の関係に限らず、社歴など経験の豊富さ、能力などの優位性を背景として行われるものも該当します。「(2)業務上必要かつ相当な範囲を超え」とは、業務上必要性がなく、業務の目的を大きく外れた言動のことをいい、「(3)就業環境が害される」とは、労働者が身体的・精神的に苦痛を与えられ、就業環境が不快なものになることをいいます。
なお、この判断基準は平均的な労働者が、同じ状況で同じ言動を受けたときにどう感じるかであり、パワハラの行為者や被害者の主観で決まるものではありません。そのため行為者が「わざとじゃなかった」「悪意はなかった」と考えていたとしても、パワハラに該当することも、被害者が「絶対にパワハラだ」「相手に悪意があるに違いない」と思っていても、パワハラに該当しないこともあります。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。