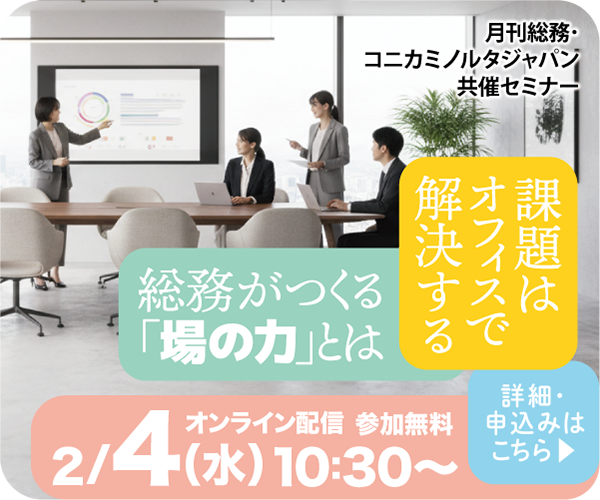健康経営からウェルビーイング経営へ ウェルビーイング経営における次の時代の職場の在り方

アクセスランキング
働く人のライフスタイル・ワークスタイルが変化する中で、健康へのニーズが高まってきています。そうした中で、社員の健康に投資することを事業成長の柱とする考え方が、ウェルビーイング経営です。しかし、健康とは個人の価値観であり、どこまで企業が踏み入ってよい領域なのでしょうか。この視点を深掘りすることで、職場の在り方を捉え直してみます。
なぜ企業が社員の健康をつくる必要があるのか
「健康は最上の善であり、他のあらゆる善の基礎である」(デカルト)の言葉にある通り、「健康であること」は年代・時代を問わず普遍的な価値観です。健康を求めることは社員の当然の権利といえるでしょう。ところが、これまでは不健康であることは個人の責任であると考えられてきました。明らかに体に害のある喫煙がやめられないことも、高血圧なのに昼食にラーメンを食べてしまうことも、本人が怠けているせいなのです。
一方、公衆衛生の世界的潮流では、健康は個人の責任ではない方向に動いています。その人の不健康が発生する要因の半分以上は社会的な環境にあるという「Social Determinants of Health」(健康の社会的決定要因、以下SDH)の考え方です。たとえば、喫煙者がたばこをやめられない要因はその人の上司が喫煙者であったり、ストレスの多い職場環境や独身生活であること、喫煙場所に容易にアクセスできることが挙げられます。本稿ではSDHの詳細については省きますが、企業が社員の健康をつくる必要性はここにあります。
つまり、社員が1日の大半を過ごし、複数のリスク要因にさらされる場所である職場環境を改善しないことには、働く人の健康はつくれないのです。SDHの考え方を知っている社員は多くないと思いますが、職場環境が健康を左右する要因であることは直感的に知っているはずです。
また、新型コロナウイルスの流行により、職場における健康管理の未熟さが問題になりました。こうした社会的機運の高まりにより、企業が健康管理を徹底する必要性が高まったのです。
ウェルビーイング経営の健康の範囲
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。