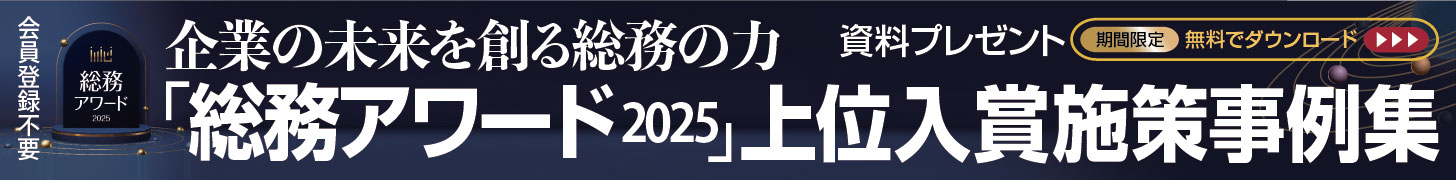ウェルビーイングの本質とこれからの在り方 ウェルビーイングの向上は企業の成長力を決定付ける

アクセスランキング
コロナ禍で一気に導入されたテレワークも3年目を迎え、各社の対応もまちまち。他方、多様な働き方に柔軟に対応している企業では、より一層、ウェルビーイングの取り組みを加速している。従業員の「働きがい」や「幸せ」は今後の企業の成長にどのような影響を及ぼすのか、専門家に解説いただいた。
取材・文◎宮本 優子
「ウェルビーイング」の国内外の動向

代表
株式会社働きがいのある会社研究所
代表取締役社長
荒川 陽子さん
2003年、HRR株式会社(現株式会社リクルートマネジメントソリューションズ)入社。顧客企業が抱える人・組織課題に対するソリューション提案を担う。2015年からは同社の組織行動研究所を兼務し、女性活躍推進テーマの研究を行う。2020年より現職。コロナ禍をきっかけに小田原に移住。自然豊かな環境での子育てを楽しみつつ、日本社会に働きがいのある会社を増やすための活動をしている。
「ウェルビーイング」(Well-being)とは、心身ともに良好な状態にあることを意味する概念であり、「健康」「幸福」「福祉」などに直訳される。この言葉が初めて登場したのは、1946年。世界保健機関(WHO)設立に向けて採択された世界保健機関憲章の中で、「健康とは、単に疾病がない状態ということではなく、肉体的、精神的、そして社会的に、完全に満たされた状態にある」と定義されている。
また、2021年12月、WHOは『幸福に関するWHOのアジェンダの開発に向けて』を発刊。その際、「SDGsには『ウェルビーイング』(健康と幸福感)という概念が結び付いている」とし、「人間開発の指標を、経済的なものから人々や地球のウェルビーイングに焦点を当てたものに変えていこうという国際的な動きが活発化する中、このような取り組みが成功している事例を集めた議論と問題提起の文書を発刊」したと述べられた。
日本では、2021年7月に内閣府が事務局となり「Well-beingに関する関係省庁連絡会議」を設置。ウェルビーイングに関する取り組みの推進に向けて情報共有・連携強化・優良事例の横展開をはかることとし、関連の基本計画等のKPIを設定した。これら一連の動きを受け、日本経済新聞(2022年1月5日付)では「今年をウェルビーイング元年に」と報じている。
「ウェルビーイング」と働きがいの相関
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。