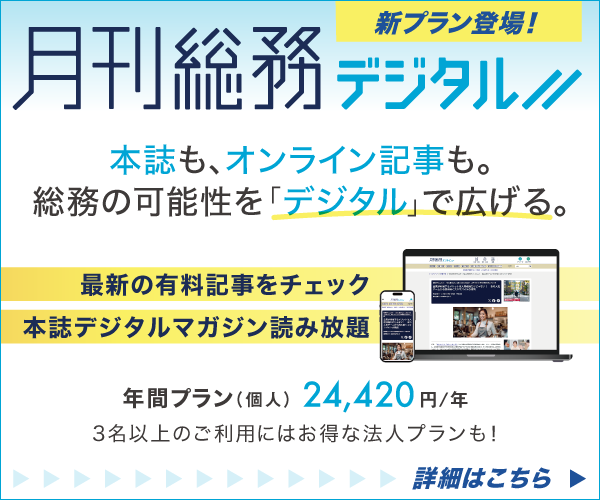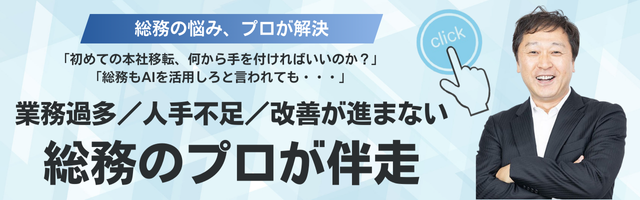1980年代の「最適化の呪縛」から脱却する 短期に小さく始めることが組織アジャイルの第一歩

アクセスランキング
長期的なビジョンが見えにくいVUCAの時代、「アジャイル」が組織運営のモデルとして注目されている。市谷聡啓さんは、ソフトウエア開発の現場で発展したアジャイルの軌跡を20年にわたりつぶさに見てきた。今、アジャイルが企業の福音として期待される背景や、ソフトウエア開発の文脈から組織運営に応用するための具体的な考え方、取り組み方についてうかがった。
取材・文◎武田 洋子
ゴールが不確定なときに福音となるアジャイル

代表取締役
市谷 聡啓さん
サービスや事業についてアイデア段階の構想からコンセプトを練り上げていく、DX推進・アジャイル支援の第一人者。プログラマー、SIerでのプロジェクトマネジメント、大規模インターネットサービスのプロデューサー、アジャイル開発の実践を経て、自身の会社を立ち上げた。『正しいものを正しくつくる』『組織を芯からアジャイルにする』(ともにビー・エヌ・エヌ)など著書多数。
アジャイルという言葉がソフトウエア開発の現場で使われ始めたのは、今から20年ほどさかのぼる2000年代初頭。当時ソフトウエア開発のフローは、「作るものを決める→仕様と作り方を決める→開発する→できたものをテストする」が主流だった。それぞれのフェーズごとに内容を精査して顧客と合意し、合意したあとは前のフェーズには戻らない。一つひとつのフェーズに完璧を期することで、間違わずにゴールに至ることができると考えられていた。
ところが、その方法がうまくいかない場面が出てくる。顧客がアウトプットのイメージを持っていないときだ。ずっと最前線にいた市谷聡啓さんに当時のようすを聞いた。
「何が正解なのかわからない場合、この方法で進めていっても待っているのは作り直しか、顧客が泣き寝入りするかの結末です。そうした状況に対応するために用いられたのが、短期間、たとえば1週間でやるべきことの計画を立てて実行し、達成できたことを確かめ、その上で次の1週間の方向性を決定していくという方法でした。これがアジャイルの原型になります。今、いろいろな人がアジャイルを定義していますが、私は『現状をよく見る→取るべき行動を判断する→取り組む、というサイクルを短い期間で小さく試していくこと。そしてその結果から次の判断や行動をより適切なものにしていくこと』に尽きると考えます」
ソフトウエア開発の業界から始まったこの手法は、なぜ広く他業界の組織にまで広がっていったのか。それは、VUCAの時代がもたらしたゴールの決めづらさに、企業が新たな解決手法を求めたからだ。市谷さんは、多くの企業でアジャイル開発のサポートを行った経験から、環境の変化に対応し切れない企業に共通する傾向を、「最適化の呪縛」と見ている。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。