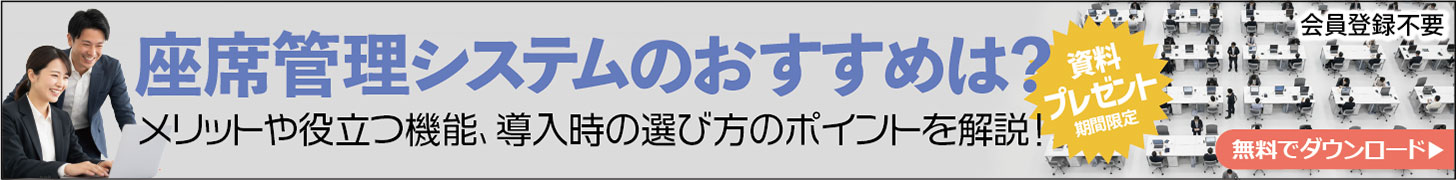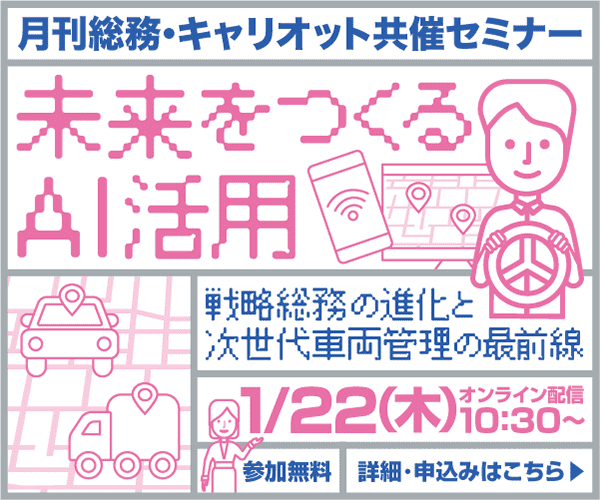総務のマニュアル
:
総務・人事担当者が知っておきたい五月病対策
コロナ禍の適応支援(4) 企業が行うべき適応支援とは
さんぎょうい株式会社 メンタルヘルス・ソリューション事業室 室長 佐倉 健史
最終更新日:
2022年05月12日
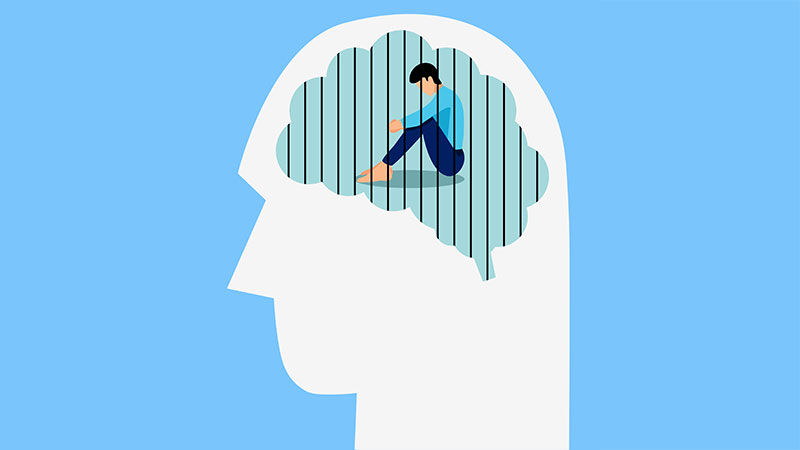
アクセスランキング
新入社員など大きな環境の変化を迎えた人が、ゴールデンウイーク明けくらいにメンタルダウンしてしまう、いわゆる「五月病」をはじめ、メンタルヘルス対策に悩んでいる総務・人事担当者の方も多いかと思います。さらに、コロナ禍でテレワークの機会が増えたことにより、労働者の状態が見えない中での対策が必要になってきています。ここでは、自社の社員が五月病に陥らないために積極的に行うべき施策と、その必要性について解説します。
コロナ禍の適応支援(3) コロナ禍におけるメンタルヘルスの状況と労働者の職場適応はこちら
社員に対して企業が負う安全配慮義務について
これまで見てきたように、五月病は、環境の変化への適応につまずき、精神的負担を感じながら一定期間耐えた先に起こるものです。そのため、企業としても社員がそれぞれの職場で過度に負担を感じることなく適応できるように支援する必要があります。
一方、多くの社員を抱える企業にとって、それぞれの適応をどこまで支援する必要があるかという疑問もあるかと思います。たとえば、ほかの社員が順調に適応しつつある中、プライベートの事情や社員のストレス耐性が低いことで1人だけ発症した場合も、企業に責任があるのでしょうか。そういった個人の事情の側面が強い人の支援を企業がする必要はあるのでしょうか。
ここで、メンタルヘルスに関する安全配慮義務をあらためて確認しましょう。企業の間でメンタルヘルスに関する安全配慮義務が取り上げられるようになったのは、2000年に最高裁で判決が出た電通事件(コラム1参照)が契機となっています。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。