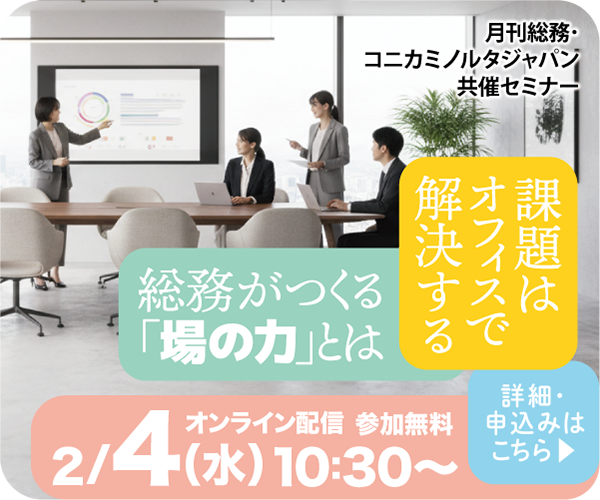コロナ禍の適応支援(3) コロナ禍におけるメンタルヘルスの状況と労働者の職場適応

アクセスランキング
新入社員など大きな環境の変化を迎えた人が、ゴールデンウイーク明けくらいにメンタルダウンしてしまう、いわゆる「五月病」をはじめ、メンタルヘルス対策に悩んでいる総務・人事担当者の方も多いかと思います。さらに、コロナ禍でテレワークの機会が増えたことにより、労働者の状態が見えない中での対策が必要になってきています。ここでは、「コロナうつ」という言葉も生まれたこの状況での職場適応について説明します。
コロナ禍の適応支援(4) 企業が行うべき適応支援とははこちら
コロナ禍初年の2020年、労働者のストレスはどう変化したのか
2015年から、従業員50人以上の事業場にてストレスチェックの実施が義務化されました。測定する内容として、労働者の感じる心理的な負荷(ストレッサー)、上司・同僚・家族への話しやすさや相談のしやすさ(サポート)、活力の低下や不安、抑うつ気分など(ストレス反応)の3つの領域が法により定められています。
2020年のストレスチェックでは、新型コロナウイルス感染症の流行による不安感やステイホームの
当時、「コロナうつ」といった言葉がマスコミに取り上げられましたが、多くの労働者にとっては通勤の負担、業務量、職場の対人関係の煩わしさが減り、ワーク・ライフ・バランスが向上し、トータルでメリットの方が上回ったことによるものと推察されます。
実際のメンタルヘルス不調者の人数を把握することは難しいですが、一つの指標として、独立行政法人福祉医療機構の2021年発表の調査では、精神科病院の外来における2020年中の月別の収益はおおむね横ばいか、減少であったことが示されています。
受診を控えた傾向もあったとは思いますが、筆者が当時所属していたクリニックや交流のある精神科・心療内科のスタッフは、患者は減ったと口をそろえていました。既存の患者さんについても、在宅勤務になり負担が減って症状が良くなり、通院頻度が下がったという話も珍しくありませんでした。
2020年はそういったマクロな動きが見られた年でした。一方、個々の事情をミクロに見ていくと、また別の側面が現れます。筆者も実際に相談を複数受けましたが、まさに本稿のテーマでもある新たな環境への適応が求められている新入社員や部署異動などのニューカマーといえる労働者、子育てや介護を担う労働者にとっては厳しい環境でした。ここで、事例を2つ紹介しましょう。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。