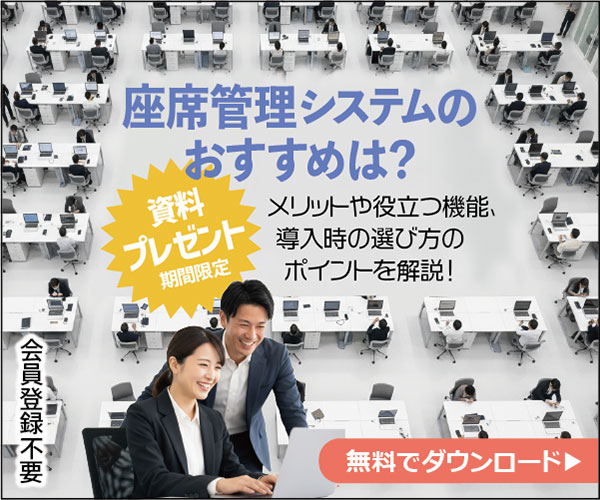アクセスランキング
パーパス経営とは何か。一橋大学ビジネススクール客員教授の名和高司さんは、その著書の中でパーパスを「志」と訳している。ニューノーマル時代に乗り出す日本企業に必要なのは、立派だけれど最大公約数的で凡庸な「大義」よりも、自社ならではの個性が光る「大志」なのだ。「パーパス経営」の本質、注目される背景、総務部門が果たす役割をうかがった。
取材・文◎武田 洋子
主観的な指標が導くパーパス経営

名和 高司さん
東京大学法学部、ハーバード・ビジネス・スクール卒業(ベーカースカラー授与)。三菱商事株式会社を経て、マッキンゼー・アンド・カンパニーで約20年間勤務。2010年より現職。株式会社ファーストリテイリング、味の素株式会社、SOMPOホールディングス株式会社などの社外取締役、アクセンチュア株式会社、株式会社インターブランドジャパンなどのシニアアドバイザーを兼任。2014年より、「CSVフォーラム」を主催。『パーパス経営』『CSV経営戦略』(東洋経済新報社)、『経営変革大全』『稲盛と永守』(日本経済新聞出版)など著書多数。
今、パーパス経営という言葉が熱い。SDGsのように、時代のキーワードとみなされ、ブームの様相を呈している。『月刊総務』の調査でも、「企業経営における『パーパス』とはどんなことを指すか知っているか」の問いに、「よく理解している」「なんとなく理解している」と回答した人が約4割。「言葉は知っている(が内容はあまり理解してない)」まで含めると、認知度は7割に上る(図表1)。
「パーパス(Purpose)」という単語は目的や存在意義と訳されることが多く、「パーパス経営」は企業の存在意義を前面に押し出した経営という印象を受ける。しかし、日本におけるブームの火付け役となった『パーパス経営』の著者、名和高司さんは、パーパスを「志」といい換えた。
「直訳である存在意義という言葉は、いかにもよそよそしく感じます。パーパス経営の本質は、『自分たちは誰にどのような価値を提供したいのか?』という問いに尽きますが、外来語に飛び付かなくてもこの精神は古来、日本人が主軸にしていたものです。『志』は士の心と書き、士とは士業に代表されるプロフェッショナルを指します。私は、道を究める求道者たちの心を表す『志』こそが、パーパスの本質を捉えていると考えました。日本の資本主義の父と呼ばれた渋沢栄一氏もまた、利益拡大を目的化しない高い倫理観と志の重要性を説いています」
パーパス(大志)は、経営理念(大義)とも違う。大義には義務感が付きまとう。世のため人のため「〜せねばならない」という、大上段に構えた使命感が先行するのだ。使命感は尊いが、創業者はともかく社員が等しく同じ気持ちにはなりづらく、結局、他人ごとになってしまう。
一方、大志は「〜したい」という気持ちが原点だ。胸を突き上げるようにわき出る想いであり、こうした情熱は共鳴者を得やすい。会社とは本来、志に共感する仲間たちの集団であるべきなのだ。掲げるのは小志ではなく、北極星のように遠くで強く光る大志が望ましい。それでこそ社員が自分ごとにしやすくなるという。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。