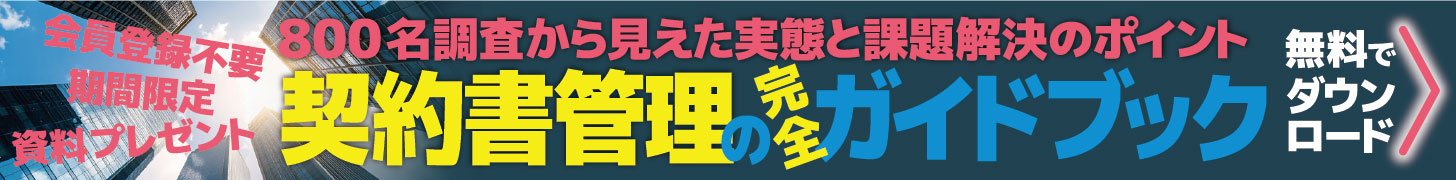不妊治療、「必要性に気付かない」企業と「相談をためらう」従業員にずれ 求められる両立支援とは

アクセスランキング
前回「不妊治療と仕事、約3割が『両立できず』。退職や治療中止を選ぶ人も 知っておきたい現状と課題」では、国内における不妊治療の現状について紹介しました。今回は企業の治療支援の取り組み状況と、不妊治療支援の導入ポイントについて解説していきます。
支援策がある企業は少数
不妊治療支援を行う企業は増えているものの、まだ限られた数にとどまっています。厚生労働省の調査によれば、支援制度を導入したり、個別に対応したりしている企業は26.5%となっています(※1)。しかし、それは一部であり、多くの企業は具体的な支援策を講じていないのが現状です。この背景には、企業側が不妊治療の実態を把握していないことや、制度設計に対する理解不足が挙げられます。
※1 厚生労働省「不妊治療と仕事の両立サポートハンドブック」
企業が不妊治療支援の必要性に気付かない主な理由として、不妊治療当事者の約6割が職場で治療のことを一切伝えていない(伝えない予定)という現状があります。実際に企業の人事や総務からは、「相談がないから対応の必要性がわからない」「自社では困っている人はいないと思う」「従業員への確認が難しい」「今まで不妊治療で離職した人はいない」などの声が聞かれます。本当にそうでしょうか。
前回も述べた通り、国内では4.4組に1組が不妊治療をしており、4人に1人が離職または働き方を変えています。その割合からすれば自社で起きていないとは考えにくいと思われます。当法人の調査によると、不妊治療を理由に退職した242人のうち45%が「家庭の事情」などと伝えて退職しており、企業側は不妊治療が離職理由であることに気付いていないことが多いのです(※2)。このような背景から、対策が遅れ、気付かないうちに多くの企業では不妊治療での離職につながっています。
※2 NPO法人フォレシア「不妊治療での離職経験者へのアンケート調査」
当事者が相談をためらうわけ
一方、当事者からは次のような声が上がります。「相談しても、理解してもらえるか不安」「プロジェクトから外されるのではないか」「プライベートについてはいいたくない」。このことから、まず前提として、不妊治療支援を行うには、大きく分けて2つのパターンを想定する必要があります(図表)。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。