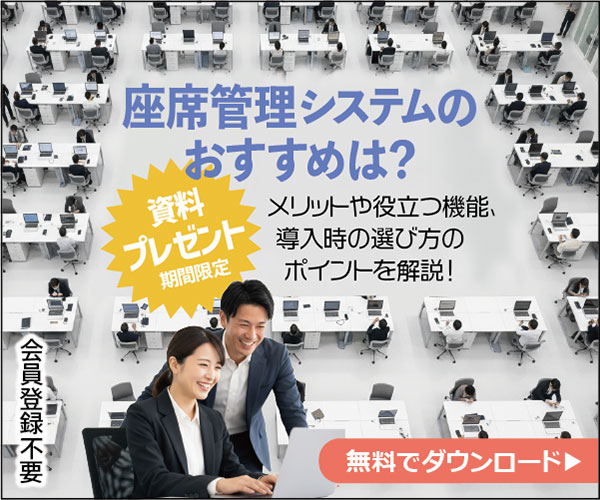若手社員が上司にアドバイス 世代間のコミュニケーションを促進する「リバースメンタリング」

アクセスランキング
若手社員がメンターとなり、上司や経営層に助言を行う取り組み、「リバースメンタリング」を導入する動きが広がっています。さまざまな世代間でのコミュニケーションが活性化することは、組織に良い効果をもたらします。本稿では2回にわたり、リバースメンタリングを行うメリットや、導入のポイントなどについて解説します。
リバースメンタリングとは
リバースメンタリングとは、年長者が年少者を指導するという従来の立場を逆転させる仕組みのことです。通常、メンタリングは、経験豊富な年長者が専門技術や知識を伝える形態が一般的ですが、リバースメンタリングの場では、たとえば入社3年目の若手社員が入社歴30年の幹部社員にアドバイスを行います。
「入社歴が浅い社員に教えられることがあるのか?」と驚く人もいるかもしれませんが、みなさんの職場でも若手社員がパソコンや最新システムの使い方を年長者に教えたり、会話の中で最新のトレンドを共有したりすることがあるのではないでしょうか。それらを制度として確立したものがリバースメンタリングです。
リバースメンタリングの発端は、1990年代のアメリカの大手電機メーカーであるといわれています。当時、普及前であったインターネットの使い方を若手社員が経営陣に教える仕組みを作り、効果を発揮したことで注目を集めました。
その後もデジタル技術の進化は加速し、特に近年では新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、多くの企業で職場のDX化が進められています。ただし、せっかく導入された最新のITツールも「わからないから使わない」と距離を置いてしまうと、組織全体の成長を妨げることになります。むしろ、新しい技術の習得や新しい環境への適応は若手社員の方が優れている傾向にあり、年少者から年長者に教える方がより良い結果を生むことも多いようです。特に最近の若手社員は、子供時代からインターネットやスマートフォンが身近にあったことで、デジタルに慣れ親しんで育ってきました。そのため新しいシステムの操作方法も感覚的にわかるという人が多いでしょう。こうした若手を生かして、世界や日本国内においてもリバースメンタリングを取り入れる企業が増えてきています。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。