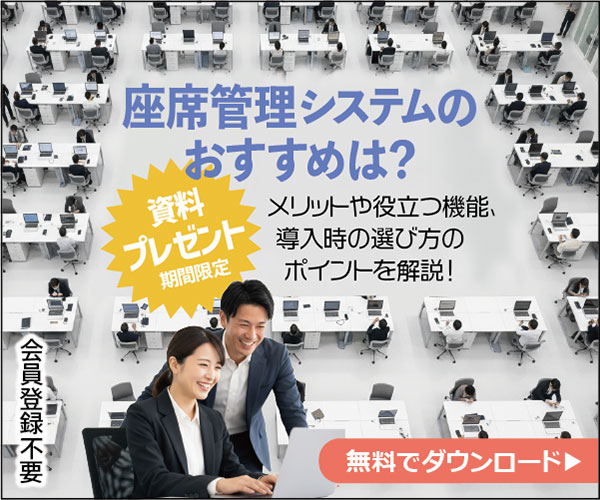「リスクごとに策定が必要」という先入観は捨てよう BCPでみんなが誤解している3つのこと

アクセスランキング
私たちの社会や経済は今、さまざまな脅威にさらされているといっても過言ではありません。大地震や未知の感染症の大流行はいつまた起こるかわかりませんし、近年は気候変動の影響もより顕著になってきました。夏は40℃に迫る連日の猛暑、春から秋にかけては桁外れの大雨がもたらす水害や土砂災害……といったことです。これに加え、みなさんの日々の業務に特有のリスクもあるでしょう。サイバー攻撃や電力需給の逼迫による停電リスク、サプライヤー側のアクシデントによる調達難、食品メーカーや外食産業では食中毒の発生や風評被害なども警戒しなくてはなりません。
こうしたあまたのリスクに、企業はどう備えればよいのでしょうか。実は、答えは考えるまでもなくすでに決まっているのです。「BCP(事業継続計画)を策定し、継続的に運用していくこと」以外に選択肢はありません。しかし、このようにいや応もない書き方をすると、大きな壁にぶち当たったような無力感を感じる読者も少なくないでしょう。そこで本連載では、BCP策定と運用のポイントをわかりやすく解説していきます。
BCPにまつわる3つの誤解
これまで筆者は、幾度となく「BCPの策定がうまくいかない」「BCPは完成したけど本当にこれで役立つのか?」「地震対応のBCPを作るだけで手いっぱい。ほかのリスクを想定したBCPを追加するなんて考えられない!」といった意見をお聞きしました。実は、こうしたネガティブな見方には典型的な3つの誤解が潜んでいるのです。
(1)防災とBCPを混同している
防災とBCPは目的・役割が全く異なります。「防災」は災害の予防と発災時の安全の確保、そして被害を大きくしないための事前対策が主な目的です。一方「BCP」は、原因が何であれ、事業活動が混乱・停止する事態に陥ったときに、主要な製品・サービスの供給を止めないためにはどのような方針と手順が必要かを網羅した計画です(図表1)。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。