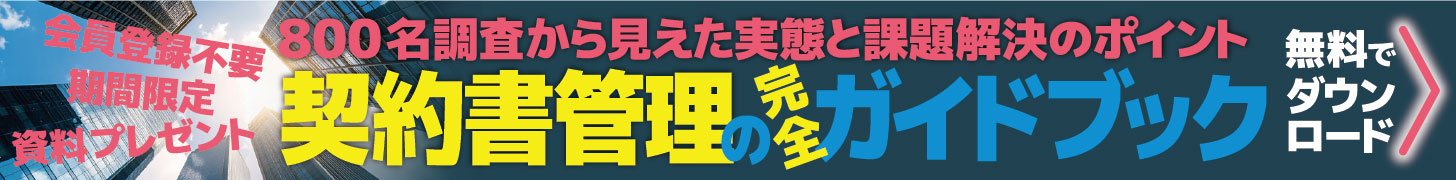上司が仕事を用意する時代はもう終わり……今、注目される「ジョブ・クラフティング」とは何か

アクセスランキング
近年、「ジョブ・クラフティング」という学術研究から生まれた考え方が、産業界において注目されています。ジョブ・クラフティング研究は、経営学・組織行動論の分野において、2001年にその考え方のルーツとなる論文が発表されたのち、2010年代に実証研究が増え始め、その後さらに10年を経て多くの論文が蓄積されてきています。日本の産業界でも注目が高まり、ビジネスパーソン向けの解説記事や書籍を目にする機会も増えました。本企画は、そんなジョブ・クラフティングについて3回に分けて解説していきます。第1回となる今回は、ジョブ・クラフティングという考え方の特徴について理解していきましょう。
2人の経営学者によって提唱されたジョブ・クラフティング。その考え方の特徴とは
ジョブ・クラフティングという考え方は、エイミー・レズネフスキー氏とジェーン・ダットン氏という2人の経営学者によって2001年に提唱されました。仕事を自分にとってやりがいや手応えのあるものに自らつくり上げている人と、そうでない人の違いに着目し、その考え方や行動をジョブ・クラフティングとして概念化しました。
彼らの初期の研究では病院の清掃員や、レストランの調理師など比較的裁量の幅が狭いように見える仕事が取り上げられていますが、その後、企業の管理職や企画職などを対象とした研究も行われています。仕事にやりがいや手応えを感じている人々は、定められたタスクを淡々とこなすだけでなく、自分の価値観や強みに合わせて、仕事のタスクや他者とのかかわりをデザインし直して(リ・デザインして)いたのです。具体例は次回ご紹介します。
学術研究論文においては、レズネフスキー氏とダットン氏による「個人が自らの仕事のタスク『境界』もしくは関係的『境界』においてなす物理的および認知的変化」という定義が必ずといっていいほど引用されます。この「境界」という見慣れない表現が、ジョブ・クラフティングという考え方の特徴の源泉となっています。
「境界」と表現されているのは、自分の仕事を決める「枠」のようなものと考えてみてください。この仕事で行うタスクはあれとこれで、その過程で誰とかかわって、こういう意味のある(この程度の意味しかない)仕事なんだ、ということを思い定める「枠」です。それは、上司や関係者から提示された「枠」でもあり、自身が思い込んでいる「枠」でもあります。この「枠」が、高くて分厚い壁に思える場合もあるでしょう。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。