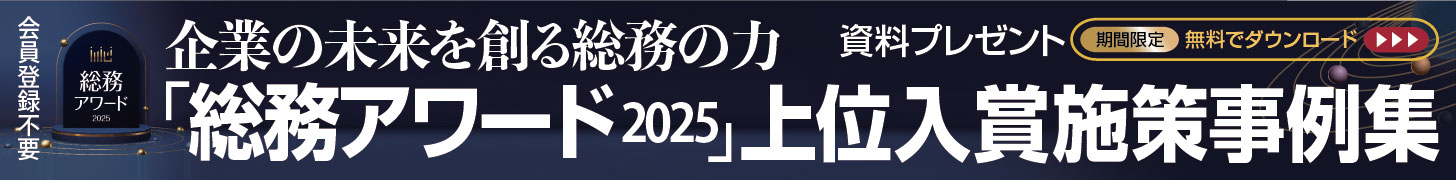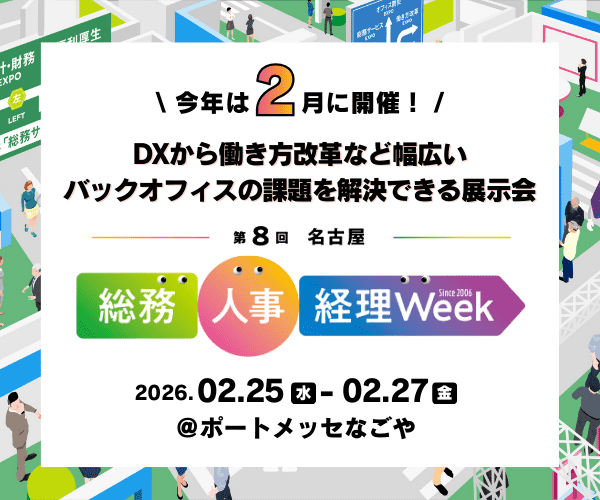アクセスランキング
多くの日本企業で、人材の成長や組織活性化の一手段として活用されてきた転勤制度。しかし、企業を取り巻く環境の変化や働き方に対する価値観の多様化等により、従業員の転勤に対する意識や企業の向き合い方も変わりつつあります。本連載では、転勤制度やその運用が見直されている背景やポイントについて解説していきます。今回は、転勤制度の現状について見ていきましょう。
企業が転勤を実施する目的
企業はなぜ転勤を実施するのでしょうか。その目的は大きく4つあります。
(1)適切な人材配置の実現
転勤制度の基本的な目的は、適切な人材配置を実現することです。全国に事業所を持つ企業では、特定の事業所で人材不足が生じたり、新規で事業所が開設されたりすることがあります。
このような場合、事業所内の異動や管轄エリア内の採用だけでは従業員の補充が難しいため、各地の状況に応じた柔軟な人材配置が求められます。
そのため、別地域の事業所と需要と供給の調整を行い、適切な人員配置を実現する手段として転勤制度が活用されています。
(2)従業員の育成
日本企業における総合職のキャリア形成では、仕事の経験の幅を広げることが重視される傾向があります。事業所や管轄エリアの枠を超えて、従業員にさまざまな環境や業務を経験させることができる転勤は、幅広い経験やスキルを持った従業員の育成において有用な手段といえるでしょう。
また、育成の対象は「非管理職」というイメージが強いかもしれませんが、管理職を対象にした経営幹部育成、経営幹部候補育成にも転勤制度が活用されることがあります。
(3)業務の属人化の防止
業務の属人化を防ぐために、転勤を活用することもあります。たとえば、営業担当者の場合、同じ顧客を長期間同じ人が担当するのではなく、異なる担当者が顧客を引き継ぐことで、売り上げの増加をはかることができます。
また、従業員にとっても新しい場所で新たな顧客を担当したり、異なる業務に取り組むことが刺激となり、モチベーションの向上につながることも考えられます。
(4)社内人材の交流
転勤には社内人材の交流を活性化する目的もあります。企業によっては、本社、店舗、工場等、働く場所が多岐にわたります。そのため、転勤を通じて異なる勤務地や業務を経験することで、一緒に働く人とのつながりが生まれ、社内人脈が形成されます。
また、従業員同士のつながりが強化されることで、業務連携もより円滑なものとなり、生産性の向上にもつながると考えられます。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。