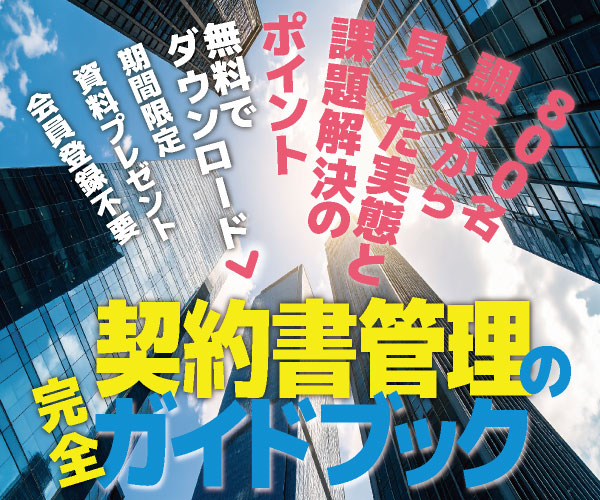従業員にとって安心・安全な職場をつくる 労働災害防止ガイド
「カスハラ」による心理的負荷も対象に 過労死、精神障がいなど労災認定基準の近年の改正ポイント
プロアクト法律事務所 弁護士 徳山 佳祐
プロアクト法律事務所 弁護士 田畑 瑠巳
最終更新日:
2025年04月15日
働き方改革が進められる中、2021年に20年ぶりに労働災害(以下、労災)の脳・心臓疾患の認定基準、いわゆる「過労死ライン」が、2023年には精神障がいの認定基準が見直され、2023年度の過重労働や仕事のストレスを原因とした労災認定の件数が過去最多になりました。そこで本企画では、労災の現状、認定基準の改正点、実際に労災が発生した場合の対応、労災防止対策などについて3回にわたって解説します。
労災の種類と労災に対する補償・支給
労災とは、労働者が労務に従事したことによって被った死亡、負傷、疾病をいいます。
労災の種類としては、
- 労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況などが原因となって発生する「業務上の負傷」
- 事業主の支配下にある状態において有害因子にさらされたことによって発症した「業務上の疾病」
- 複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする傷病等の「複数業務要因災害」
- 通勤によって労働者が被った傷病等の「通勤災害」
の4つがあります。
労災が発生した場合、当該事業主は、労働基準法により補償責任を負うことになりますが(労働基準法第75条以下)、労災保険に加入している場合は、労災保険による給付が行われ、事業主は労働基準法上の補償責任を免れます。
ただ、たとえば、事業者において、労働者が長時間の過重労働をしており、健康状態が悪化していることを知りながら業務軽減措置等を取らなかった場合など、事業者に注意義務違反が認められる場合には、労働基準法上の補償責任とは別に、労働者やその遺族から不法行為・債務不履行(安全配慮義務違反)などにより民法上の損害賠償請求がなされることもあります。なお、この場合には、二重補てんという不合理を解消するため、労災保険により補償が行われたときは、その価額分は民法による損害賠償の責任を免れます。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。
アクセスランキング
特別企画、サービス
-
【編集部厳選】総務1年生にオススメしたいコンテンツ20本
『月刊総務』編集部が、総務1年生やこの春久々に総務業務を担当する方にオススメのコンテンツを厳選。この機会に、総務実務の基本はもちろん、ビジネススキルや総務の考え方について学んでみませんか? -
総務のマニュアル
総務・バックオフィスの実務を実践的にサポートする「総務のマニュアル」シリーズ。ビジネストレンドを押さえた内容で、いま総務が知っておきたいポイントを具体的に解説していきます。 -
多様な働き方に対応する 社内コミュニケーション術
リモートワーク、ABWなど働き方の多様化がさらに広がっています。対面のコミュニケーションが減っている中においても、コミュニケーションを活性化するために、どうしていくべきでしょうか。 -
テレワークを実現するペーパーレス化と文書管理のポイント
ハイブリッドワークの需要が高まったものの、総務・経理などの管理部門では、請求書や契約書など書類のデジタル化に対応できず、出社を余儀なくされた方も多いのではないでしょうか。 -
総務辞典
総務辞典とは、どなたでもご利用いただける、総務業務に関する一般知識、関連法令や実務ノウハウなど総務に関する用語辞典です。 -
無料オンラインセミナーのご案内
月刊総務が開く、無料オンラインセミナーの予定はこちらからご確認ください。さまざまな企業と共催し、より専門的な知識を幅広いテーマで発信。総務の皆様の情報収集にお役立てください。 -
『月刊総務』調査
『月刊総務』では、不定期にアンケート調査を実施し、その結果を公開しています。全国の総務パーソンがどのように業務に対応しているのか、何を感じているのか、総務の現状を確認してみましょう。 -
YouTube 月刊総務チャンネル
『月刊総務』公式YouTubeチャンネルです! 「働き方」「戦略総務」などのテーマについて、数分で気軽にキャッチできる情報を発信していきます。ぜひ、チャンネル登録をお願いします! -
メンタル不調者が増える6月前にチェックしておきたい10本
ゴールデンウイークが明け、退職代行サービスの利用者が急増しているようです。新卒・若手社員の早期離職が深刻化し、五(六)月病が話題になっています。気象病と仕事のストレスが重なる6月に向け、メンタルヘルス対策を紹介します。 -
業務効率化&コスト削減 購買プラットフォーム
オフィス用品に関する困りごとを解決し、業務効率化とコスト削減を実現いたします。Kobuyは、一貫堂が提携するパートナーサプライヤに加え、お客様ご希望のサプライヤ商品・サービスを一元管理できるオフィス用品一括購買システムです。