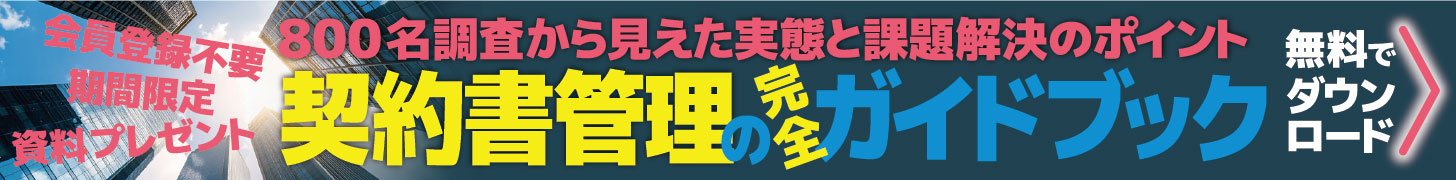勤務間インターバルや副業の割増賃金など、働き方改革に合った労基法見直し 厚労省研究会のまとめ
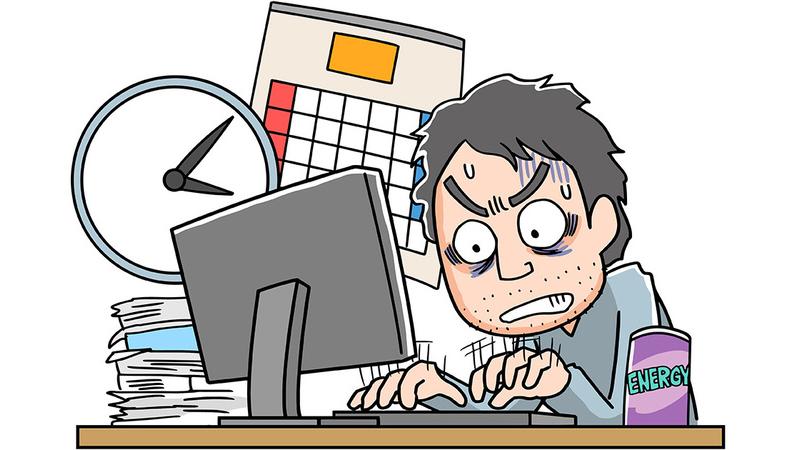
アクセスランキング
厚生労働省の有識者研究会である「労働基準関係法制研究会」(座長=荒木尚志東京大大学院教授)は11月12日、多様な働き方に対応するための労働基準法見直しに向けた最終的な報告書の骨子案にあたる「議論のたたき台」を示した。
同研究会は、経済学者らによる「新しい時代の働き方に関する研究会」(座長=今野浩一郎学習院大学名誉教授)の報告書を引き継ぐ形で、2024年1月に発足。労働政策審議会の議論にのせる「前段」となる場で、主に法律の専門家らで構成し、次の時代の労基法を見据えた幅広い議論を展開している。
骨子案には勤務間インターバル制度の導入促進に向けた法規制強化の必要性が示されたほか、14日以上の連続勤務の禁止や副業している人の割増賃金の計算方法の見直し、フレックス制の導入といった労働時間法制の見直しの提言が盛り込まれた。
勤務間インターバル制度は「11時間の休息」を軸に検討
終業から次の始業までに一定の休息時間を設ける勤務間インターバル制度では、11時間の休息を軸に導入促進に向けた法規制強化の検討が必要だとした。
勤務間インターバル制度は、現在は努力義務となっており、導入企業も約6%にとどまっている。
たたき台では、11時間の休息時間を原則としつつ、適用除外やインターバルが取れなかった日の代替措置などを法令や労使合意で広く認めることや、規制適用に経過措置を設けることなどで「より多くの企業が導入しやすい形で制度を開始し、段階的に実効性を高めていく形が望ましい」との意見がまとめられた。
一方で、具体的な義務化の度合いについては、労基法による強力な義務付け、措置義務や配慮義務といった罰則なしの義務化、現在の抽象的な努力義務規定の具体化といった案を併記し、「さまざまな手段を考慮した検討が必要」とした。
テレワークにも「フレックス制」導入へ 柔軟な働き方をあと押し
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。