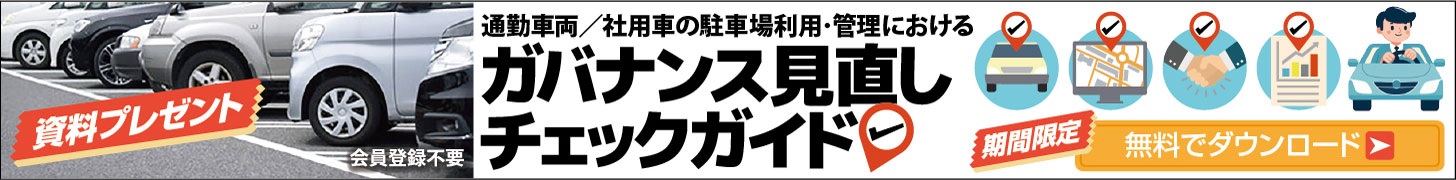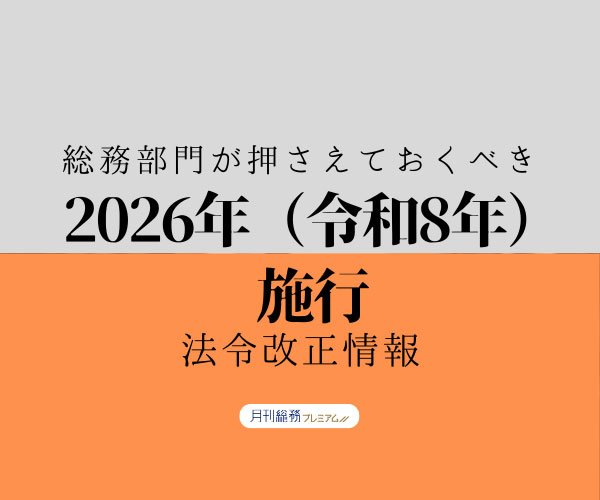仕事と介護は両立できる
仕事と介護は両立できる【第4回】いたずらに介護休暇を与えれば介護離職を後押しする
NPO法人となりのかいご 代表理事 社会福祉士/介護支援専門員/介護福祉士 川内 潤
最終更新日:
2020年09月14日

アクセスランキング
これまでの活動での気付き
2020年現在、年間450人以上の介護に相談に応じる中で、相談者の多くが「親の介護は自分や家族が直接するべき」という認識を持ち、多くの人がそれに苦しめられていることに気が付きました。直接介護に携わることができないと罪悪感を抱き、直接介護をしてもいずれ行き詰まり、介護離職や家族に対する虐待につながってしまうケースがあるのです。
そこで当法人は、相談者に「(直接的な)介護は専門職に頼り、自身は家族にしかできないかかわり合いをしてほしい」ということを訴え続けています。企業の人事・労務担当者には、「仕事と介護の両立は、大事な人材を失わない」という企業のメリットだけではなく、「家族が介護に直接かかわり過ぎることによって発生する問題」についても理解を広げ、その対策などを提案してきました。
介護による離職要因調査の実施
介護相談を行う中で、「親の介護は自分や家族が直接するべき」という認識がある以上、「介護に関する企業制度を充実させ利用促進することは、介護離職を後押ししてしまうのではないか?」という仮説が浮かび上がりました。この仮説に基づいた調査・検証を行い、その結果をまとめたのが、「介護離職白書 ― 介護による離職要因調査 ―」です。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。