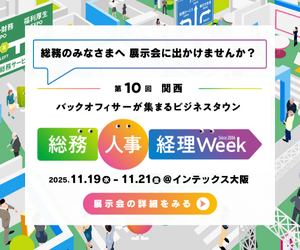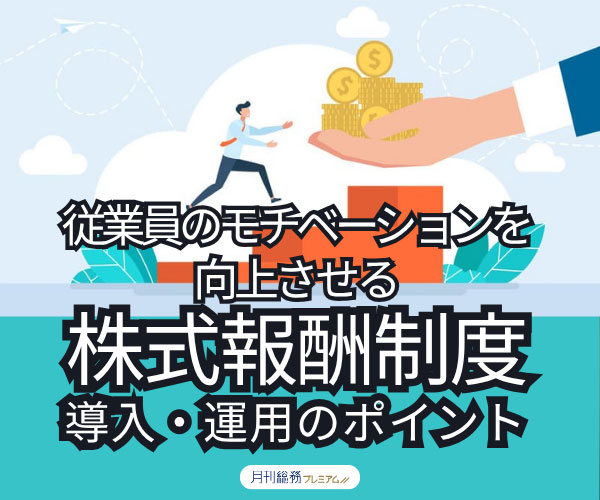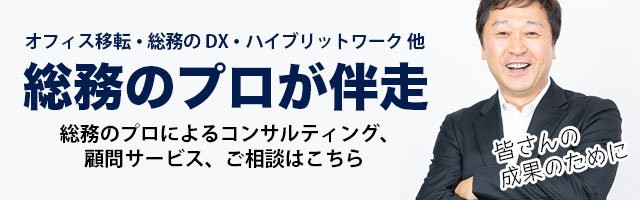経費削減&コア業務へのシフトを実現するBPO
経費削減&コア業務へのシフトを実現するBPO【第4回】イノベーションを成功に導く秘訣「業務可視化」
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 企画担当 高桑 敬太
最終更新日:
2021年02月18日
アクセスランキング
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。