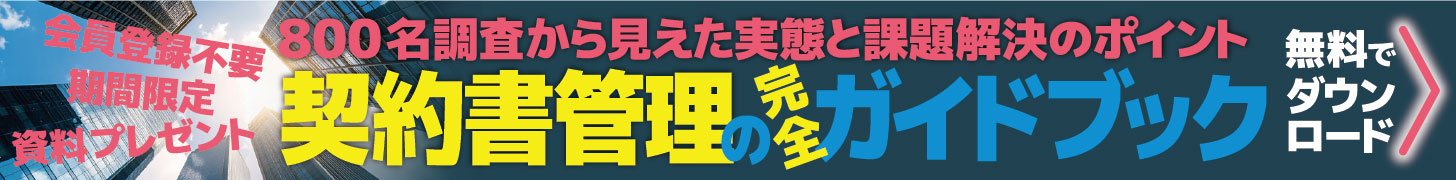アクセスランキング
Withコロナ・Afterコロナの時代に、変化に強い組織のつくり方として、ワークフローシステムの導入を提案する本シリーズ。第4回となる今回は、ワークフローシステム導入による具体的な効果として「BCP(事業継続計画)」をご紹介します。
BCPの基礎知識
頻発する自然災害や新型コロナウイルスに代表される世界的パンデミック、デジタル技術の飛躍など、私たちは今まさにVUCA時代の真っただ中にいるといっても過言ではありません。そのため、目まぐるしく移り変わる変化にいつでも対応できる組織づくりをしておくことが企業にとってとても重要になります。
変化に強い組織を作るための方法の一つとして提案したいのがBCPの策定です。有事の際の行動指針をあらかじめ計画として策定しておくことで、緊急事態が発生しても事業を中断することなく早期復旧することを目指します。
BCPには表記や意味がよく似た言葉がいくつか存在します。混同しないようにするためにも、まずは代表的なものを整理しておきましょう。
BCM
BCMは「Business Continuty Management」の頭文字を取った言葉で事業継続マネジメントを意味します。
BCPが緊急事態発生時において事業を継続、または早期復旧させるための計画そのものであるのに対し、BCMは計画の策定から運用、改善までの一連のプロセスを指します。
BCS
BCSは「Business Continuty Strategy」の頭文字を取った言葉で、事業継続戦略を意味します。BCPを実行するための具体的な戦略として、下記のようなものが例として挙げられます。
- 在宅勤務
- 二重化(設備を複数拠点に設置する)
- 他社との相互支援協定
- アウトソーシング
- 経営統合・合併
- 新たな事業へのシフト
- 現地復旧
- 代替施設・敷地の準備
企業防災
大震災など災害が発生したときに、従業員や取引先などの安全を守るための災害対策を指します。BCPが、有事の際における事業継続、または早期回復を目的としているのに対し、企業防災では、被害の最小化を目的としています。
業務継続計画
BCPとほぼ同じ意味で使用されます。ただし、BCPが主に企業を対象としているのに対し、業務継続計画は行政機関や介護業界が対象となります。
BCPの必要性
次に、BCPの策定がなぜ重要なのか、BCPの必要性について詳しく見てみましょう。
事業縮小や倒産リスクの軽減
BCPが策定されていないと、いざ緊急事態が発生したときに迅速に対応することができず、中核事業を停止せざるを得ない状況に追い込まれる可能性があります。
さらに、停止された事業再開までのプランを最初から考えなくてはならないため、再開のめどが立った頃には、顧客が競合に流れてしまい、事業縮小や倒産といったことにもなりかねません。
従業員の不安を解消
BCPが策定されていない、もしくは不十分な場合、それは、前述のように事業縮小や倒産のリスクを常に抱えていることになり、従業員からしてみると、失業など深刻な影響も考えられるため、大きな不安要素になります。
優秀な人材の流出やとり逃しを防止するためにも、BCPの取り組みを積極的に行うべきであるといえます。
社会的信用の獲得
取引先や投資家などのステークホルダーからしてみても、事業縮小や倒産のリスクは少ないに越したことはありません。
また、いざ緊急事態が発生したときに、迅速にそれに対応することで、企業としての存在感をアピールでき、引いては社会的信用の獲得や、ブランドイメージの向上につながります。
BCPの策定状況
最後にBCPの実施状況について見てみましょう
内閣府が2022年1、2月に実施した「企業の事業継続及び防災に関する実態調査」によると、2021年の時点で、大企業が70.8%、中堅企業では40.8%の企業がBCPを策定しており、両者とも前回の調査(令和元年実施)と比較して割合が大きくなっていることから、今後ますます増加すると考えられます。
その一方で、中小企業についてはその限りではありません。中小企業庁の「2022年版中小企業白書・小規模企業白書」によると、2021年時点でBCPを策定している中小企業の割合は15%となり、「現在、策定中」(7%)、「策定を検討している」(24%)を合わせても半分に満たない状況です。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。