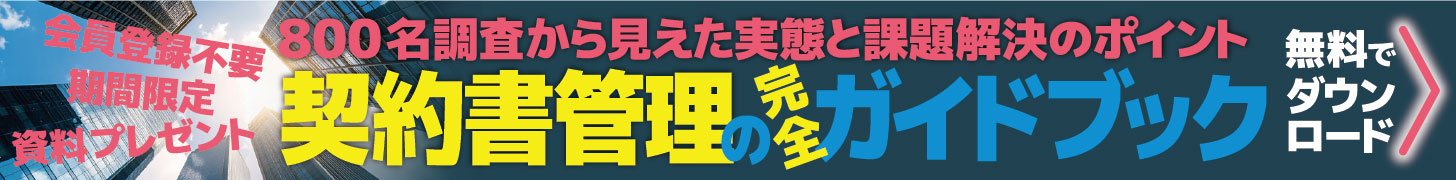総務のマニュアル
:
取得する側も送り出す側も働きやすい職場に 育児・介護休業の手続きと体制整備のポイント
仕事が分配される側にも配慮 休業を「お互いさま」で終わらせない、働きやすい職場のつくり方
社会保険労務士 佐佐木 由美子
最終更新日:
2023年11月20日

アクセスランキング
前回「従業員から『産後パパ育休』の申し出、総務が対応することは? 育児・介護休業取得の手続きフロー」では、育児・介護休業に関する手続きの流れを中心に解説しました。今回は、休業への職場の理解促進と支援をどのように進めていくか解説するとともに、企業が受けられる推進支援金等について紹介します。
働きやすい職場環境づくりには経営幹部層に理解があることが大前提
従業員の希望に即して育児・介護休業を取得できるようにするためには、育児・介護と仕事の両立が可能で働きやすい職場づくりは欠かせません。
その第一歩として、経営トップから両立支援の意義や取り組みについてメッセージを発信することは、非常に重要です。就業規則等の規定をはじめ、いくら雇用環境を整備しても、職場において育児・介護休業が取りにくい雰囲気が払拭されなければ、制度が活用されることは難しいものです。
女性の育児休業に関しては寛容であっても、男性が育児休業を取得することにはいまだに抵抗感を示す経営者が少なくありません。育児・介護によって離職する従業員をなくし、働きやすい職場環境づくりをすることが、どれほど経営においてメリットがあるか、経営幹部層が理解することは大前提といえます。
その上で、部長クラスを男性の育休推進者として巻き込んでいけると、浸透スピードも加速するでしょう。人事評価項目に部下の育休を取得させたかどうかを対象に含めるなどすると、部課長クラスにおいて取得推進へのインセンティブが高まります。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。