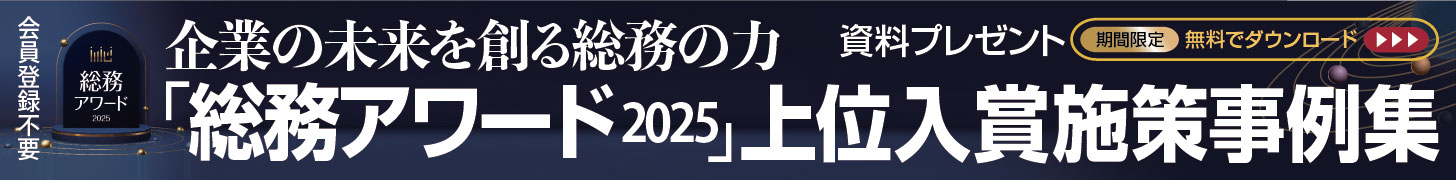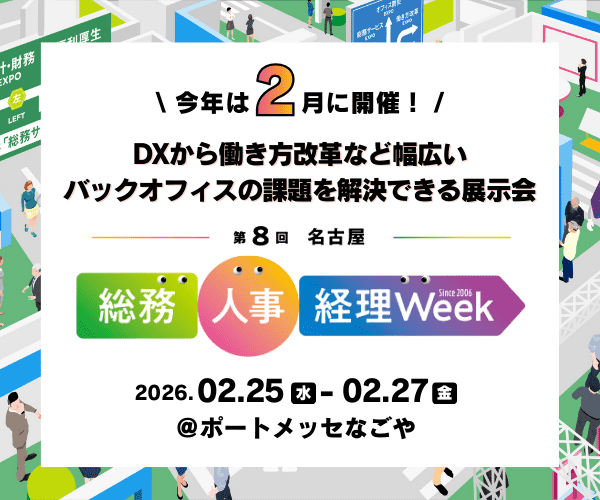総務のマニュアル
:
今から押さえておきたい インボイス制度対応マニュアル
インボイス制度開始で企業が対応しなければならないこととは
株式会社TOKIUM 代表取締役 黒﨑 賢一
最終更新日:
2023年01月17日

アクセスランキング
インボイス制度に対応するために、企業は何をする必要があるのでしょうか。「インボイス発行事業者への登録」「売り手側としての準備」「買い手側としての準備」について解説します。
インボイス発行事業者の登録
まずはインボイス発行事業者の登録要否を判断する
前提として、インボイス制度導入後にインボイスを発行できるのは、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)への登録申請を行った課税事業者のみです。また、インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかは企業の任意となります。
登録要否を判断するポイントの一つとして、自社の取引先がインボイスを必要とするかを判断材料にしてみましょう。自社の主な販売先が消費者や免税事業者である場合には、仕入税額控除を行わないため、インボイスは必要ありません。
また、簡易課税制度を選択している場合は、インボイスを保存しなくとも仕入税額控除を行うことができるため、インボイスを必要としません。
しかし、それ以外の課税事業者である販売先は、仕入税額控除のために、売り手が交付するインボイスの保存が必要となります。
自社の顧客がインボイスを必要とするか確認し、インボイス発行事業者へ登録すべきかどうか検討してみてください。
インボイス発行事業者の登録を受けた場合
自社がインボイス発行事業者となった場合は、取引の相手方(課税事業者)の求めに応じて、記載事項を満たした適格請求書(または適格簡易請求書)を交付する義務があります。
免税事業者もインボイス発行事業者の登録を受けると、基準期間の課税売上高が1000万円以下でも課税事業者として申告する必要があります。
インボイス発行事業者の登録を受けなかった場合
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。