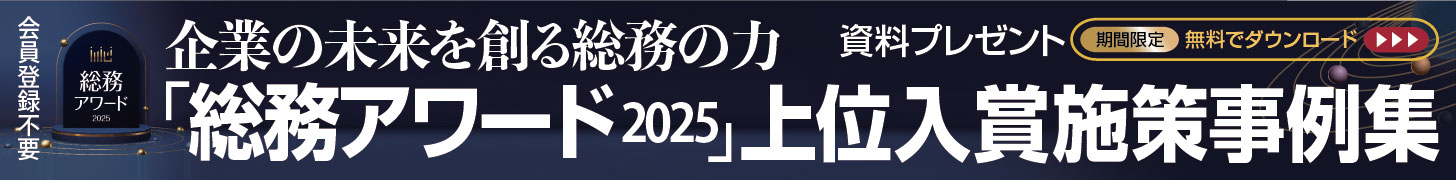「株価は高ければ良い」の認識は危険! 新NISA時代にIR活動の効果を上げるポイントとは

アクセスランキング
第1回ではIRとは何か、第2回ではIRの仕事について解説しました。最終回となる今回は、IR活動の効果を上げるポイントを解説します。第1回の中で、IRのミッションは必要な資金をスムーズに調達できるようにすること、具体的には、自社の株価が安すぎたり高すぎたり、激しい値動きをしたりしないよう適切な評価をしてもらえるようにする、多くの投資家が売買してくれるようにすることだとお伝えしました。つまり、IR活動を通じて上げるべき効果とは「適正株価の実現」「ボラティリティ(価格変動の度合い)の低下」「流動性の向上」の3点です。それぞれ何をすればよいのか、見ていきましょう。
「適正株価の実現」に必要なこと
「株価は市場が決めるもの」ではあるのですが、IR活動が十分でない場合、つまり自社が持つ本来の価値やポテンシャルが投資家に理解されていないと、過小評価されたり、逆に過大評価されていたりします。「株価は高ければいいのでは?」と思われるかもしれませんが、過大評価された株はメッキが剥がれた瞬間に暴落するリスクがあり、「ボラティリティの上昇」を招いてしまいます。会社にとって、株価は高すぎても安すぎても良くありません。ですから、積極的な情報発信と投資家の疑問点や誤解の解消によって、適正な評価をされるよう取り組むことが必要です。
たとえば、IRサイトや統合報告書・株主通信等のIRツール、会社説明会などを使って、自社を取り巻く事業環境の説明、事業内容が難しい場合は業界外の一般の方(自分の親など)にもわかるよう映像やイラスト等による解説、専門用語がある場合は用語集の掲載、社員インタビューなどによる会社や商品・サービスの魅力紹介、ESG関連や人的資本経営の取り組み紹介等、さまざまな角度から情報発信を行い理解促進をはかります。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。