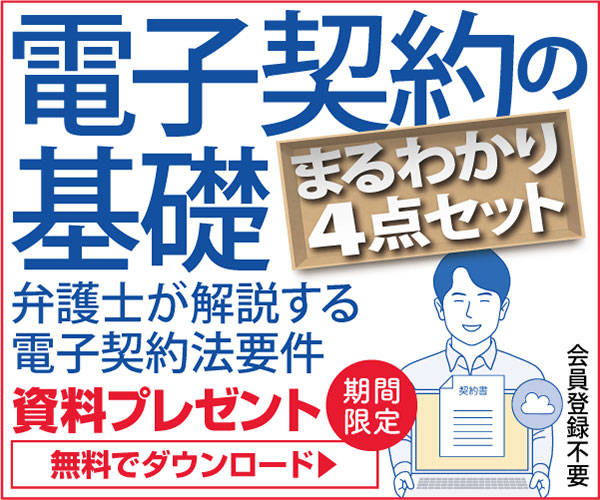BCP発動! 誰に、どんなメッセージを伝えるべき? 緊急時コミュニケーションの3つのポイント

アクセスランキング
前回は、インシデントが発生してから初動対応を通じて収集すべき情報と、その収集手段や共有方法について解説しました。これらの情報は、被害や影響の大きさをいち早く見極めるために必要な判断材料となります。その結果、人や事業へのインパクトが軽微ならば、速やかに事態を収拾し、通常業務体制への復帰を目指します。
一方、今まさに事業が止まっている、あるいは放っておくと事業に深刻な影響が及ぶと予想するなら、手遅れになる前に「アクション」を起こさなくてはなりません。この「アクション」とは、非常事態下でも製品やサービスを供給できるようにする、主要な顧客やサプライヤーに連絡して各社に最善の対応策を取るよう促す、最短で復旧するための体制を整えるといったことです。いずれのアクションも、実行に移すためには社内外のさまざまな利害関係者に目下の状況を伝え、行動を開始してもらう必要があります。こうした緊急時のコミュニケーション(第4回で紹介した図表1「危機発生~事業継続対応の4つの活動要件」(2)の部分に相当)を開始するタイミングは「BCPの発動」とも呼ばれ、BCPを特徴付ける活動要素の一つとなっています。今回はこのBCPの発動について解説していきます。
どのようなときにBCPを発動するのか? 緊急時コミュニケーションのポイント
BCPを発動する判断の目安は、「命の危険や著しい健康被害につながる事態か?」「会社の収益や財務に著しく悪影響を及ぼす事態か?」「会社の信頼・信用が著しく損なわれる事態か?」など、円滑な事業活動を阻害するような事態であるか否かが鍵となります。ときどき、避難誘導や安否確認作業の開始のことをBCPの発動と呼んでいる会社を見かけますが、これらは正しい使い方ではありません。本質的な意味を取り違えると、BCPの発動の前後の区別がつかなくなり、活動の意義や目的が薄まってしまうので注意が必要です。
BCPの発動を通じて緊急時のコミュニケーションを迅速かつタイムリーに行うためには、それぞれの伝達の目的と、その対象者を明確にしておくことが肝要です。
(1) 危機対応チームメンバーの招集
インシデントによっては、BCPの発動の判断が経営者と側近の数人で行われることもまれではありません。この段階で対策本部の設置と危機対応チームの全メンバーをそろえる必要があるならば、直ちに号令をかけて参集を促します。
(2)コア業務の継続と復旧活動に必要なスタッフの招集
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。