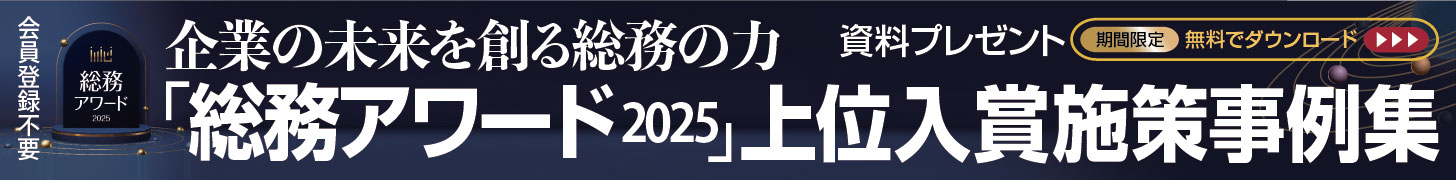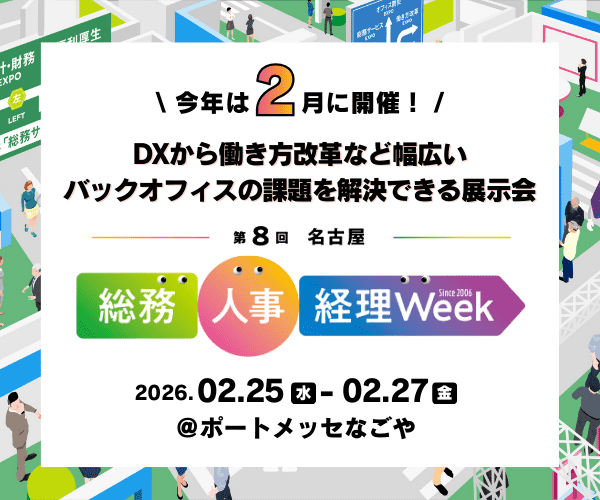アクセスランキング
障がい者の法定雇用率が2.3%に引き上げられたことで、都心部を中心に障がい者の採用市場は激化している。テレワークの普及は、「働きたい障がい者」と「採用したい企業」にとって有効な選択肢だが、留意が必要な点も多い。さまざまな形で障がい者雇用を支援する株式会社スタートラインの吉田瑛史さんに、企業が押さえるべきポイントを取材した。
取材・文◎武田洋子
社内の協力を仰ぎ安定的な業務を創出

マーケティングディビジョン
コンテンツチーム リーダー
吉田 瑛史さん
パナホーム株式会社(現パナソニックホームズ株式会社)、株式会社マイナビにて、通算で約10年間営業職に従事したのち、パーソルグループ特例子会社を経て株式会社スタートラインへ入社。これまで300社、2,000人以上の障がい者雇用・採用に携わる。現在はマーケティング部門にてコンテンツ制作やセミナー講師などを担当。
「まず、業務の創出において難しい点は、前述したように社内が協力的でないことに加え、特に精神障がいの場合は特性が個々に違うことにあります。『何が得意で何を苦手とするのか』は百人百様なのです。この難点を克服したある企業の例を紹介しましょう。その企業ではまず専門チームを立ち上げ、丁寧にチーム構築と業務レクチャーを行い、障がい者の成果物を社内に紹介することから始めたそうです。具体的に『この人はこれができる』という例を提示することで採用のメリットを他部署にも感じさせ、それならこの業務も依頼したい、という意識を社内に醸成することに成功しました。具体的な成果物から社内理解を広げるというスマートなやり方ですね。トップダウンより、現場からの働き掛けの方が共感を得やすいようです。
一方で、業務に関して重要なのは当事者に『会社に貢献している』実感があることです。転職者の多くが口にするのは、自分は法定雇用率を維持するためだけの存在だと思わされるむなしさです」
一人ひとりの特性に合っていて、多過ぎず少な過ぎない仕事量で、貢献の実感が得られる業務。それを吉田さんは「安定的な業務」と呼ぶ。切り出しからマネジメントまですべてを自社で行うには時間も労力もかかるが、在宅支援サービスを利用する方法もある。吉田さんはこれまで多くの会社から、自社事業には切り出しできる業務がないとの声を聞いてきた。しかし豊富な経験からすると、接客業であろうとテレワークであろうと、実際は切り出しできると断言する。悩んでいる間にプロに相談した方がよさそうだ。
採用は客観的な事実で判断
テレワーク雇用の成否を分ける入り口は採用だが、オンライン採用になって一層重要度を増すのが、採用基準の明確化だ。そのポイントは、客観的な事実を根拠とすることにある。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。