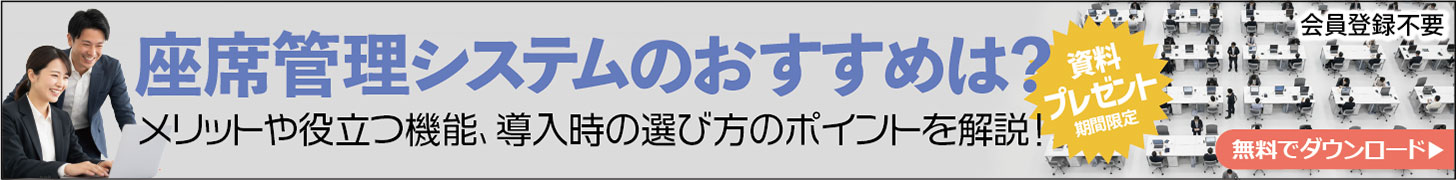採用ブランディング
採用ブランディング【第2回】なぜ集めた中から選ぼうとするのか
むすび株式会社 代表取締役 ブランディング・ディレクター/クリエイティブ・ディレクター 深澤 了
最終更新日:
2018年04月09日
アクセスランキング
ほしい人物像が決まらなければ、メッセージが甘くなる
「ほしい人材像は?」と聞いて、明確に答えられる企業は実はそう多くありません。また、それが採用にかかわるチーム全体に共有されている企業となると、ほぼ皆無に近いという印象があります。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。