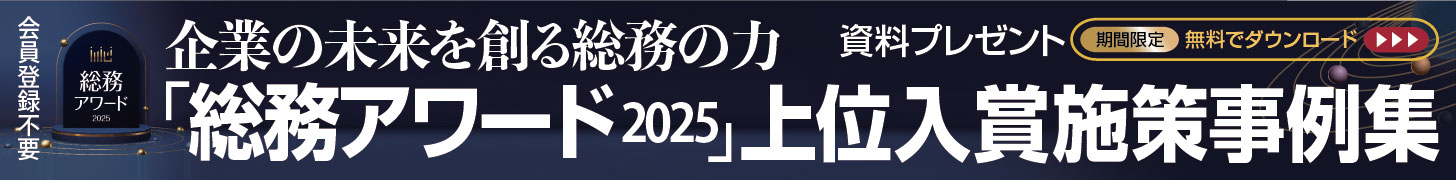アクセスランキング
ペーパーレス推進、業務改善、人事異動、ハイブリッドワークのコミュニケーション不足など、目まぐるしく変化する社会とともに総務の課題も多様化する。「月刊総務プレミアム」会員を対象とした2回目のオンライン勉強会では、異業種から7人の総務パーソンが集い、意見交換を行った。
取材・文◎武田 洋子
「『月刊総務』オンライン勉強会」開催概要
- 開催日時:5月20日(火)18:00~19:00(懇親会19:00~19:30)
- 開催方法:オンライン(Zoom)
- 参加者
- Aさん:リース・レンタルサービス。BCP領域をメインに総務歴5年
- Bさん:ITサービス。社員500人。庶務関連とオフィス改善を担当
- Cさん:ICTサービス。社員500人。営業からの異動で総務歴6年
- Dさん:情報資産管理サービス。社員800人、パートタイマー1200人。総務歴6年
- Eさん:オフィスデザイン設計。社員21人。総務とビル管理を兼任
- Fさん:ソーシャルメディア。社員1500人。総務は細分化されチームが分かれている中で、庶務の領域を担当
- Gさん:製造。社員40人。これまで総務部はなく初めての立ち上げ。
- ファシリテーター:月刊総務代表 豊田 健一
テーマ1:ウィズコロナの働き方
コロナ禍でペーパーレスは進んだか
リモートと出社のハイブリッドワークにより、オフィス環境は変化している。総務パーソンに課せられる使命もまた、新たなステージに入った。
Aさんの会社ではペーパーレスが推奨されている。しかし、「会議の紙資料禁止」や「在宅とのハイブリッドワーク」といった掛け声は勇ましいものの、ITに疎い年配社員まで巻き込んだムーブメントには至らず、もどかしい状況だ。コロナ禍を機にペーパーレスに成功した他社ではどんな取り組みをしていたのか。
「以前から両面印刷など『1枚でも紙を減らす』ルールはありましたが、やはりコロナ禍が追い風になりました。経理が在宅勤務中も請求書が届いてしまうため、取引先にお願いして支払い関係書類のPDF化を徹底したんです。それがいちばん効果的でした。この2年間、新しい紙の補充はしていません」(Fさん)
「当社も請求書のPDF化と、法務部が契約書を電子化したことで一気に郵便物が減りました。昨年からはクライアント向けのシステム導入説明会もオンラインになり、分厚いテキストが廃止されています。出社しないで済むよう必要に迫られての施策でしたが、コスト削減をはじめ、SDGsの観点からもメリットが大きかったと思います」(Bさん)
コロナ禍でデジタル化を一気に進められた企業に共通するのは、自社内だけでなく取引先の理解も得ることのようだ。
リアルイベントやオンラインツールで交流
ハイブリッドワークはまた、コミュニケーション課題も浮き彫りにした。エンゲージメント低下により、入社後1年以内の離職も珍しくなくなっている。
コミュニケーション貯金のない新人を心配したEさんの会社では、感染者数が落ち着いたタイミングで、全員がPCR検査を受けた上で社員旅行を決行した。参加は自由としたが、多くの社員が喜び、「救われた」という声もあったという。「社員数が少ないからこそできたギリギリの判断だった」とEさんはいう。
恒例だった忘年会の代わりに本社のグラウンドにキッチンカーを呼び、夕方から予約制でテーブル席を用意するイベントを開催したGさんの会社や、新社屋に照明を落とした一画を作ったところ終業後は自発的にバーが開かれ、みんなが楽しみにしているというFさんのオフィス事情など、各社とも交流の施策を工夫しているようだ。
また、Fさんの会社は新社屋移転に伴い、Slack上に全社横断のチャンネルを開いた。近辺のお勧めランチ情報など新入社員から役員まで自由に話せる場になり、オンライン上でもいいコミュニケーションが取れているという。
「コミュニケーションを積極的に取りたくない人もいて、どう巻き込んでいけばいいのかと悩んでいました。イベントを開催してもそういう人は参加しそうになくて。でも、オンライン上に場を作るというのは参考になります。うちはTeamsを使っているので、全社共通で使える新しいチャンネルを作ってみるのは一つの方法ですね」(Bさん)
コミュニケーションの活性化はいまだに過渡期の課題であり、会社によって正解もまちまちだ。さまざまな事例を参考に、試行錯誤して自社に合う形を見つけていくしかない。

テーマ2:多様な業務の効率化
総務部の負担をいかに軽減するか
工場を持つGさんの会社では、人事異動のたびに大量の名刺やユニフォーム、スリッパなど備品の手配が生じる。一度に200〜300人の辞令が出るため、その前後は総務部門全員が残業し、マンパワーで乗り切っているそうだ。ほかの参加者も、その多くが広報や株主総会運営、経理、人事など幅広い業務を兼任している。効率化は共通の課題だ。
「名刺については、人事部と共通のプラットフォームを使い外注する仕組みにしています。人事異動のデータをほぼそのまま使用して、2人体制でダブルチェックをしつつ、150人分の名刺を2日で作ります」(Aさん)
「当社は発注者が自分でシステムに入力する運用です。デザインはかなりパターンを絞っており、統一性が損なわれることはありません」(Gさん)
Eさんは、外注やITシステムを活用しながらも、繁忙期は一時的に営業や事務方の社員に業務の一部を委譲するという。膨大な総務の業務を軽減するために、他部署の協力を仰ぐということだ。これは総務部の理解者を増やし、属人化を防ぐことにもつながる。そこから、話題は「総務の属人化」へと移っていった。
悪しき属人化を防ぎつつ専門性を高める
Dさんの会社では総務経験が長くなるほど精鋭化し、代わりの人材が入りづらくなっている。しかし「その人しかわからない」状態は、いざというときに混乱をもたらすことは必至だ。
Gさんの職場では3年前からメインとサブの2人体制で業務を担当する体制を導入した。一時的には効率が落ちたが、最終的に1人が休んでも対応できるようになり、メリットの方が大きかったという。上司と部下で共有できない秘匿性の高い情報についてはマニュアルを残すなど、BCPの観点からも準備はしておくべきだろう。
Cさんが、属人化を体現する共有フォルダの整理術について他社の取り組みを尋ねた。
「データの中で、毎月更新するものはGoogle Driveへ、契約書のPDFなど変わらないものはBoxへ振り分けています。チーム内でそれぞれに共有フォルダはどんどん増えますが、これまで必要な資料が探せなかったことはないですね」(Fさん)
「検索で同じような名称がいくつも出てきてしまわないということは、社内の用語が統一されているのでしょうか。ツールの使い分けは、なるほどと思いました」(Cさん)
総務パーソンはどのくらいで異動するのだろう。「入社後に配属されたらずっと総務」という会社もあれば、「5年くらいでローテーション」という会社もあった。ジョブローテーションは属人化を防ぎ、新たな化学反応で業務を改革するチャンスになる。その一方、特にグローバル企業では総務部一筋で専門性を高めるという働き方が浸透している。
「当社も長い人は10年以上ですが、前例を踏襲するばかりではいけないと反省しています。視点を変え、これまでの知識を活かした上での変化を目指したいですね」(Dさん)
防音対策や社員アンケートなど、他社の工夫を知る機会に
ほかにも、オフィス会議室の防音問題や社員の声を吸い上げるアンケート事例など、「もっと詳しく聞きたい」内容が多く、いずれは勉強会の一環としてオフィスツアーも計画したいところだ。
「月刊総務プレミアム」会員向けの勉強会は今後も不定期で開催予定。多くの方の参加をお待ちしている。
第3回オンライン勉強会は現在準備中です。予定が決まり次第、サイト上よりご案内いたします。
3年半ぶりに再開するリアル交流イベント「第42回『総務サロン』」はお申し込みを受付中です。「総務サロン」は総務担当者同士の交流し、日々の課題や今後の総務の在り方の検討など、自社の総務業務に役立てていただくための総務の異業種交流会です。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。