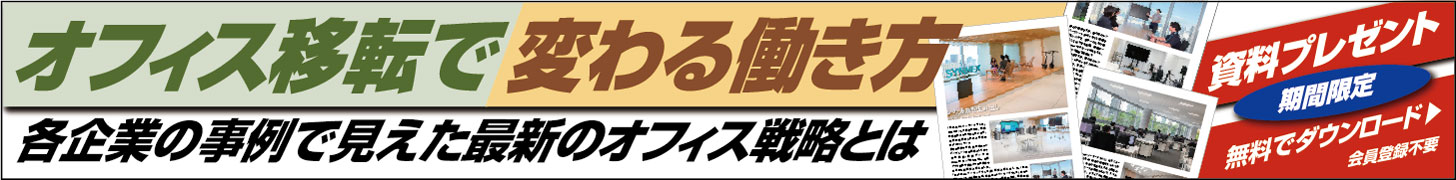組織を活性化する「場」作り
組織を活性化する「場」作り【その8】コミュニケーション・ファシリテーター
一般社団法人日本ライフシフト協会 理事、岡田経営戦略研究所 幸福価値創造コンサルタント 代表ソーシャル・プロデューサー、FOSC 副代表理事 岡田 大士郎
最終更新日:
2018年11月08日
アクセスランキング
組織のサイロ化、縦割り組織、部門間の壁......これら組織の弊害となる状態の原因は、社員同士の相互協力意識の不足と情報共有の欠如、いい換えれば組織内のコミュニケーション不全です。
ここでは組織内で面識のない社員同士が「話してみよう」「聞いてみよう」と思う動機付けを促し、抵抗感なく話しかける共通話題や雰囲気を自然体で提供するコミュニケーション・ファシリテーションの仕掛け作りと、ファシリテーターの役目について考えてみましょう。
社内コミュニケーションの場の構築・運用
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。