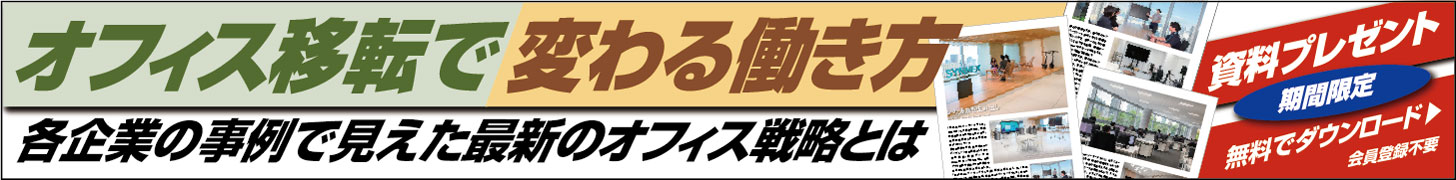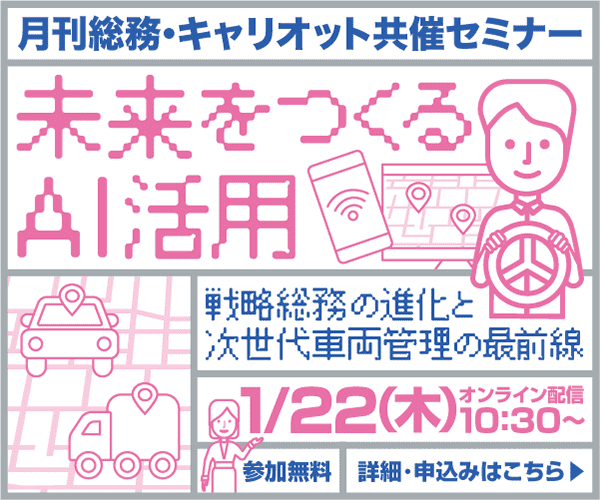業績に効果が出る新しい組織風土改革の進め方
第30回:働き方改革と業務の効率化(テレワークのコミュニケーション)
株式会社 カレンコンサルティング 代表取締役 世古 雅人
最終更新日:
2020年05月27日
アクセスランキング
4月上旬より続いていた新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による緊急事態宣言が、ようやく全面解除となりましたが、引き続き、みなさんの会社でも在宅勤務が継続されているところもあるかと思います。
今回は、前回の後編となる予定でしたが、『月刊総務』最新号(2020年6月号)におけるテレワーク特集にも絡めて、Web会議やオンラインミーティングのコミュニケーションについて一緒に考えてみましょう。
Web会議・オンラインミーティングで困ったこと
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。