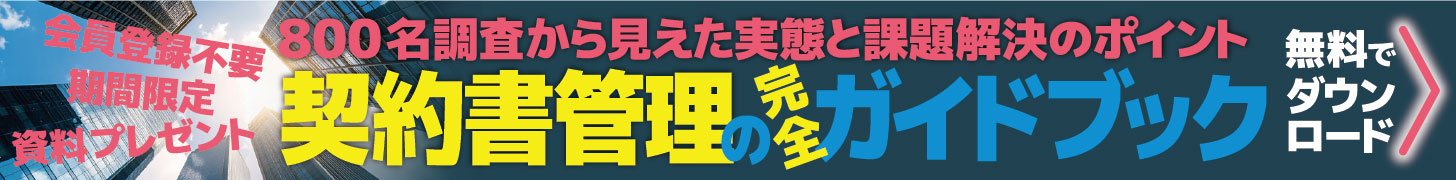自社の常識は他社の非常識? 会社独自の価値観「組織文化」を社会に合わせて変えていくには

アクセスランキング
今回は、「組織文化」がどのように生まれるのか、環境の変化に合わせてどのように変革すればよいのかを解説します。
自社にとっての“当たり前”とは
2025年の初めよりマスコミなどの報道では、株式会社フジテレビジョンの事案が連日大きく取り上げられています。問題の真相や原因などは、同社が設置する第三者委員会などに委ねるべきで、その論評はこの記事では差し控えます。ただ、こういった企業の不祥事などが起きるたびに、「なぜ、そういったことが起きるのか?」「社会や世間の常識とその企業の感覚や常識が異なっているのでは?」という疑問を持つ人も多いかと推察します。
ただ、一つの組織に長く属していると、知らず知らずのうちに、“その組織の当たり前”が“一般の当たり前”であるかのように思えてくるのも人間の自然な感情です。筆者は前職で多くの企業のコンサルティングに携わる機会がありましたが、企業ごとに考えや価値観が異なることを多くの場面で体感しました。組織論の研究では、企業に共有される価値観を「組織風土」や「組織文化」という言葉で説明がされます。今回は、組織で斉一的な価値観や考えが生まれてくる過程を振り返り、それを変革するためのポイントについて考察します。
「組織風土」や「組織文化」については、さまざまな研究がなされていますが、ここでは「組織風土は共有された知覚(shared perception)であるが、組織文化は共有された仮説(shared assumption)である」という定義に基づいて解説します。これは、桑田耕太郎・田尾雅夫著の『組織論』(初版)のp.186で、アシュフォードが唱えた説から引用された定義です。
組織は、その目的達成のために、組織図を描き、メンバーの役割分担や仕事の進め方を決めて推進していきます。その過程で、個々のメンバーは自分が何をすれば報われ、何をすれば指摘・指導されるのか理解していきます。その認識は当初個人でばらついていますが、時間が経過する過程で共通の理解に収斂していくのは一般的です。その理解が共有された状況が組織風土であり、その理解が個人の内面に規範化され一定の考え方(価値前提)になり、無意識のうちにそれに沿った行動や発言を行う状況が組織文化といわれます。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。