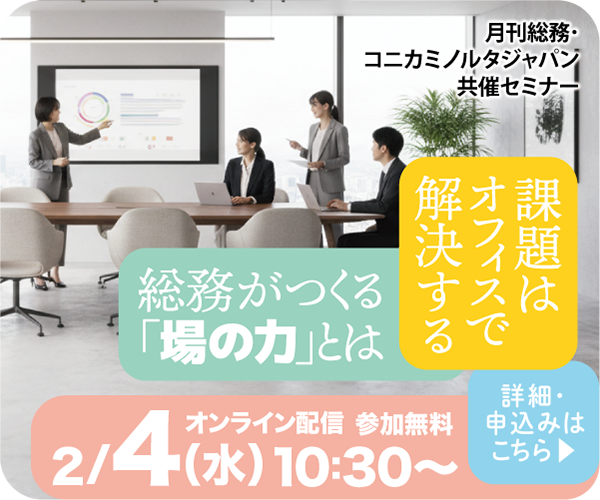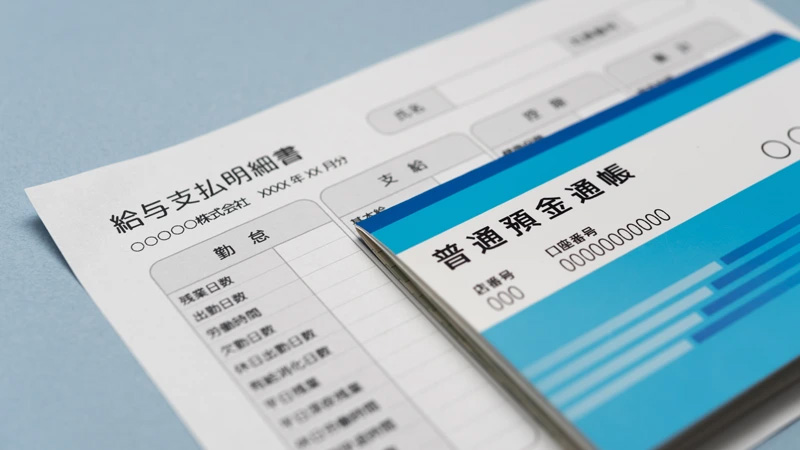
アクセスランキング
2025年度がスタートしましたが、その前段の賃金改定では初任給の引き上げが多くのマスコミで取り上げられ、話題となりました。10万円以上引き上げる会社などもあり、初任給が30万円に到達する大手企業も多数現れてきています。 先日、ある中堅企業の社長が「このまま、初任給が上がり続ければ、どうなるんでしょうね」とお話ししていました。大手を追いかけて中堅・中小企業も引き上げていけば、全従業員への波及も考えると、日本企業の人件費支給額も支給率も大きく引き上がることになります。ただし、全ての企業が追随できるわけではなく、今後賃金水準について悩まれる企業も多いかと思います。今回は、その将来の方向を探りたいと思います。
時代とともに変わる「初任給」
将来の方向を見通す際のヒントになる材料は、直近行われている大手企業の初任給の引き上げ方にあります。たとえば、東京海上日動火災保険株式会社では、2026年度入社の新卒社員から初任給を最大41万円程度にまで引き上げるとの発表がありました。しかしながら、同社のHP等で条件を調べると、改定前まで設定していたエリア総合職を廃止して総合職に一本化した上で、「転居・転勤なし」の場合は28万円程度の初任給となり、「転居・転勤あり」で、なおかつ実現した場合にサポート手当を含め最大41万円程度まで支給されることとなっています。すなわち、転居・転勤に対する対価が大幅に上がったことが見て取れます。
また、富士通株式会社では、2026年度の採用より処遇や採用時期が一律となる新卒採用を取りやめると発表しました。これらからは、企業は自らのニーズ、たとえば転勤可否や事業に必要なスキルに合わせて、賃金水準や採用方法を変えてくるという方向性が読み取れます。一括採用の見直しや職種別の賃金などなど、採用形態や賃金水準の多様化が進むということでしょう。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。