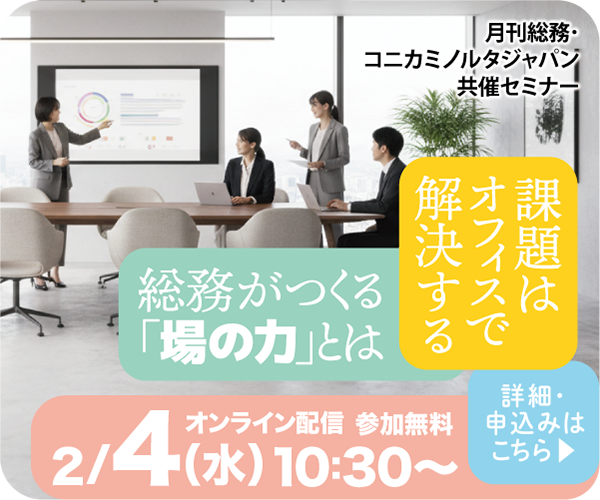解雇規制緩和の実現で広がる「会社への裏切られ感」 企業が取り組むべき被害者意識の解消法
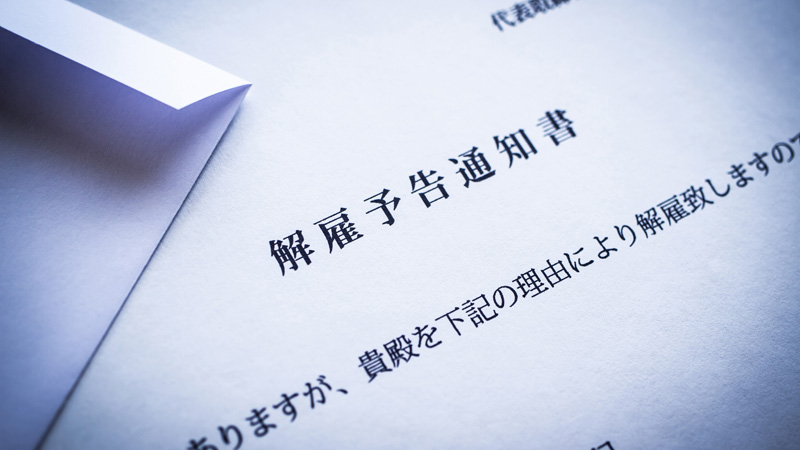
アクセスランキング
自由民主党の総裁選挙では石破氏が選出され、10月末には衆議院総選挙が行われます。その総裁選には過去にない9人が立候補し、多岐にわたるテーマで論戦が交わされましたが、「解雇規制緩和」もその一つです。規制緩和により雇用を流動化することが日本経済の活性化に本当につながるのか? 流動化することで社会はどう変わるのか? 広範囲に影響を与えるテーマです。労働法上や労務管理の観点からも多様な議論が交わされるでしょう。今回は、「解雇規制緩和」が実現した場合に、企業単体で予想される現象や従業員の反応について検討します。その上で、企業がとるべき対処方法について考えます。
「心理的契約」で成り立っている日本の雇用
「解雇規制緩和」が実現した場合、何らかの理由(業務量が減った、該当職務がなくなった、従業員のスキル・能力の不足やミスマッチなど)があれば、一定の金銭を支払うことで、企業は一方的に従業員を解雇することができるようになるとします。では、これに対して従業員はどう感じるでしょうか? おそらく「裏切られた」という感情を持つ人が多数になるでしょう。日本では「よほどのこと」がない限り、(特に正社員は)一方的に解雇されることはないと多くの人が信じているからです。
多くの日本企業ではいわゆる「メンバーシップ型」の雇用を前提としており、終身雇用が行われているのがその理由だという指摘もあります。ただ、「終身雇用」は制度やルールとして企業が従業員に明示したものではありません。就業規則に定年制は規定しますが、定年年齢まで「雇用を保障する」という規定はなく、むしろ解雇についての規定がされているのが当たり前です。「終身雇用」はメンバーシップ型雇用で組織運営を行った結果として、暗黙的に約束されたようなものなのです。
この組織と個人の「暗黙的な約束」という現象を説明する考え方に、「心理的契約」という概念があります。心理的契約とは、カーネギー・メロン大学のデニス・ルソーによれば、「特定の個人と相手方の間での相互での交換における諸条件に関する個人の信念(individual’s beliefs regarding the terms and conditions of a reciprocal exchange agreement between that focal person and another party.)」と定義されます。
この心理的契約のおもしろいところはあくまで個人側の「信念」、すなわち主観的な「思い」や「理解」とされている点です。組織運営の中で個人が経験を重ねるうち、約束されたと信じるに至ったものであれば、心理的契約として成立していると考えます。組織(企業)との間に規則や制度、ルールとして明示されている必要はありません。
この心理的契約が、組織側の都合で内容を一方的に変更される、相互の解釈のずれが積み重なる、などにより個人が「約束が守られていない」「裏切られた」と認識することがあります。その場合には、組織コミットメントの低下や離職意思の高まりなどマイナスの反応が見られることが、多くの研究で実証されています。
現在、多くの日本企業の、多くの従業員が雇用に関して抱く心理的契約の内容が「終身雇用であり、よほどのことがない限り解雇はされない」というものであれば、たとえ規制緩和が行われ、合法的に解雇が成立しても「裏切られた」という認識からくるマイナス感情は避けられないでしょう。その「裏切られた」という認識は解雇されなかった従業員にも同様に広がるため、組織全体のマイナス感情へと波及することは、心理的契約の理論から導くことができます。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。