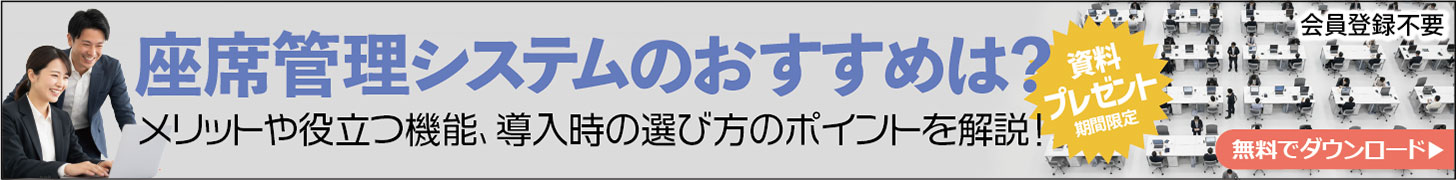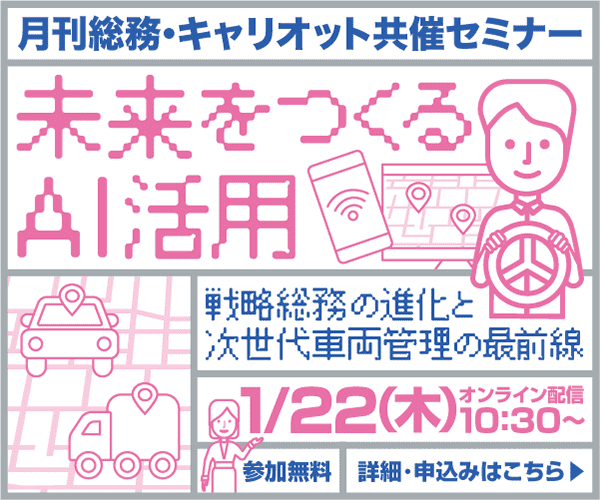人事評価の「調整」で不満が生まれてしまう理由とは? 納得感の高い制度にする仕組みと考え方

アクセスランキング
今回は、人事評価に調整が必要となる背景を踏まえつつ、従業員の納得感を高めるための方法について解説します。
人事評価で発生する「結果の調整」
春の給与改定や夏の賞与支給も終わり、総務・人事のみなさんもほっとされている時期ではないでしょうか。
給与や賞与の決定には、多くの企業で人事評価の結果を反映されていると思います。一定期間での従業員の仕事ぶりや成果・業績を評価する仕組み(ここでは人事評価と呼ぶ)は、多くの企業で当たり前に実施されています。業種や職種、企業規模や形態によって評価する内容は千差万別ですが、評価の進め方は多くの企業で同じような流れになっているのではないでしょうか。
対象従業員の直属の上司(課長など)がまず一次評価を行い、その結果を部門ごとにまとめて部長など部門責任者が二次評価を行う。最終的には企業全体でまとめて結果を最終決定する。二次・三次評価などの全体で集約するまでのステップの数は企業規模によって異なりますし、大きな企業では組織全体でまとめず事業所や事業本部で最終決定されることもあります。最終結果を本人にどうフィードバックするかなどなど、細かなバリエーションの違いはありますが、おおむね進め方は同様の流れをたどります。
そして、このプロセスで必ず発生するのが評価結果の「調整」です。一次評価者の評価結果を全て最終結果とする企業はないでしょう。一次評価の段階では甘辛など評価結果にばらつきが生じやすく、また全体の昇給や賞与予算との関係もあり、最終までに結果を修正せざるを得ません。多くの企業では、この調整方法に悩まれているのではないでしょうか。その原因と対応について考えていきます。
人事評価を通じて従業員のモチベーションアップにつなげる2つの方法
まず、人事評価の目的を問われたとき、「従業員のやる気・モチベーション向上」と答える企業は多いでしょう。がんばってもがんばらなくても、何も評価されず処遇も同じでは誰もやる気が高まらないからです。そのため、人事評価を通じて「従業員のやる気・モチベーション向上」をはかるわけですが、それが成立するメカニズムには2つの経路があります。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。