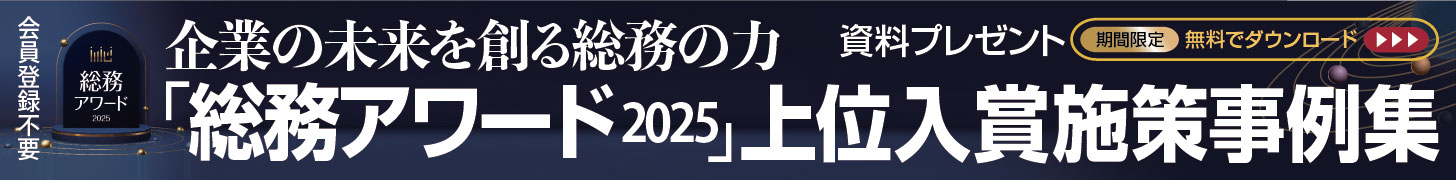知って得する!印紙税講座
知って得する!印紙税講座 第8回: 2以上の課税事項が併記又は混合している文書の所属の決定(前半)
堀 龍市税理士事務所 所長 堀 龍市
最終更新日:
2013年02月28日
アクセスランキング
前回、一の文書に2以上の号の課税事項が記載されている文書を印紙税法基本通達第10条にもとづいて大きく3つに分類しましたが、今回はいよいよ具体的な所属の決定について見ていきたいと思います。
具体的な所属を決定するためには、「課税物件表の適用に関する通則3(以下、通則3という。)」というルールに従って判断していくのですが、それでは実際にこの規定にもとづいて具体的な例を見ていきましょう。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。