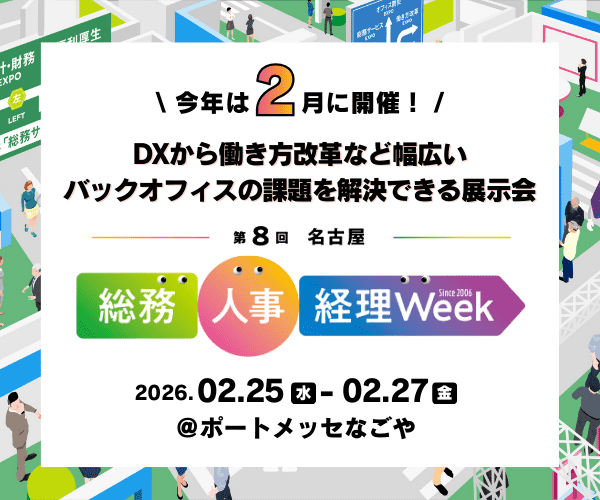メンタルヘルス不調になる前の備えこそ重要 従業員へのセルフケア教育を成功させる3つのポイント

アクセスランキング
今回は、厚労省が指針に定める「4つのケア」の一つであるセルフケアを従業員に教育することの有効性と課題を紹介します。
セルフケア教育が必要な理由
みなさんの会社では、従業員にセルフケアについての教育や情報提供をしているでしょうか。「厚労省の指針から見る 総務部門が押さえておくべきメンタルヘルス対策立案の基礎」でお伝えした通り、企業にはセルフケアを含む4つのケアが求められています。また、WHO(世界保健機関)からも、2022年に職場のメンタルヘルスに関するガイドラインが出ており、従業員にセルフケアを教育することが推奨項目に挙げられています。
セルフケアを実現するための一般的な方法としては、ストレスチェックの個人結果で気付きを与える、研修やセミナーなどで集合教育をする、eラーニングを受講させる、冊子を配布する、相談できる環境をつくるといった施策が取られます。自分の不調になかなか気付かないことも多いので、実務ではまず優先的に管理職にラインケアを教育します。管理職が気付いて適切に対応ができるようにすることで、不調の発生や悪化、再発を防止することが有効です。その際の原則として、メンタルヘルスの予防教育はトップマネジメント層から順に管理職層、チームリーダー(係長・主任クラス)層と進めていき、最後に一般社員にセルフケアを教育しましょう。これは各層に対して、すでに上司はラインケアの教育を受けているため、あなたが相談したらきちんと対応してくれるのだという一定の保証を与えた上で、縦のラインの相談を研修の中で促す意図があります。
一方で、小規模の店舗・営業拠点を多く抱えるような企業や客先常駐、間接部門においてメンバーが複数の事業場に分散しているため上司が直接対面でマネジメントしづらい場合など、会社や管理職によるケアを従業員に届けることが難しい職場も多くあります。そうした場合の対策は主に下記の3つです。
(1)縦ラインの接触機会を増やす
(2)遊撃部隊的なサポート役を専任で配置して巡回や相談対応をさせる
(3)セルフケア教育を優先して実施する
ちなみに(2)は適切に運用すれば大きな効果がありますが、同時に課題もあります。名だたる大企業でさえ、それに気付かないままリスクの高い対応をしている例が見受けられるのです。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。