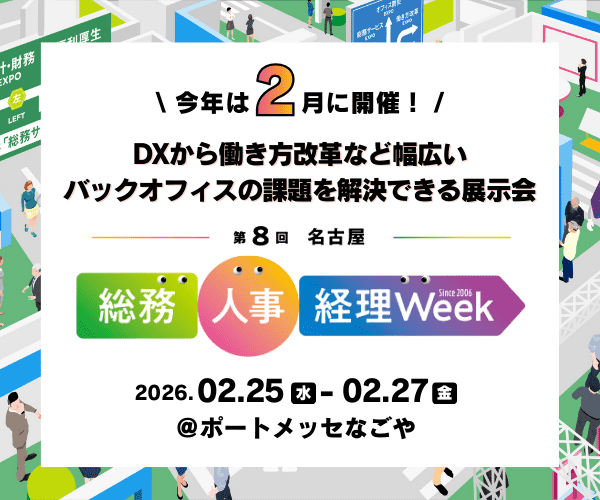社員の問題行動、原因は性格? それともメンタルヘルス不調? その判断方法と必要な対応

アクセスランキング
今回は、メンタルヘルスの個別対応や制度設計で必要になる問題整理の視点を紹介します。
問題行動の原因は性格か病気か
攻撃的な言動で周りに迷惑をかける、必要のない企画書を大量に作成した上に上司を飛び越え勝手に役員にプレゼンする、実態のない職場のいじめをたびたび訴えてくる……。職場で問題行動を起こす従業員がいた場合、読者のみなさんはその原因がメンタルヘルス不調かもしれないという発想をどの程度持てるでしょうか。実はこうした行動にはメンタルヘルスの問題が背景にあることを念頭に対応することが必要ですが、性格傾向や考え方の問題として捉えてしまうパターンも少なくありません。
一方で、メンタルヘルス不調であっても、必ずしも問題があり、配慮が必要なわけではありません。たとえば、ある管理職が部下から精神科に通院していることを聞いたため、あまり負荷をかけない方がよいと独自に判断して業務配分を他の部下に寄せたとします。この管理職の対応は本当に必要なのでしょうか。職場での問題行動について、原因が病気なのか性格なのかという問いは古くからあり、一昔前は過度に後者であると断じてしまい、必要な配慮がされないという傾向がありました。しかし現在では、コンプライアンス遵守の流れからか、前者であると思い込み過度な配慮がされることが増えてきているように感じます。
4月は公私ともに自身や身の回りで環境に変化が起こりやすく、メンタルヘルス面で不調に陥る従業員が増える時期でもあります。また、ゴールデンウイーク明けには、4月からの過度な緊張からくる疲労などが一気に表面化して調子を崩し出社できなくなるという、いわゆる「五月病」と呼ばれる状態に陥る従業員が出てくることもあるでしょう。そのため、この時期は総務担当者として、メンタルヘルスの問題を正しく切り分ける必要性が特に高まるといえます。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。