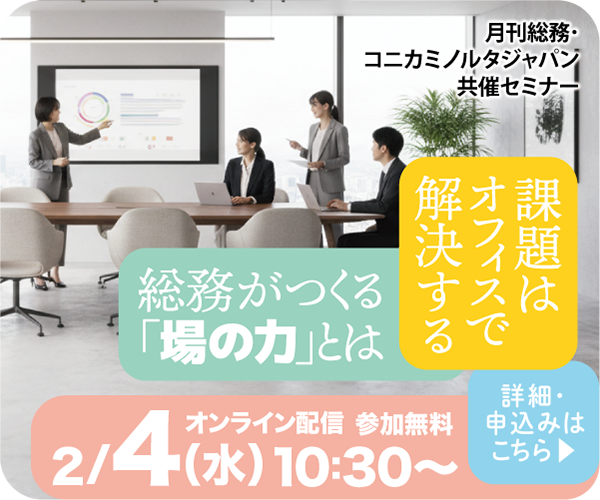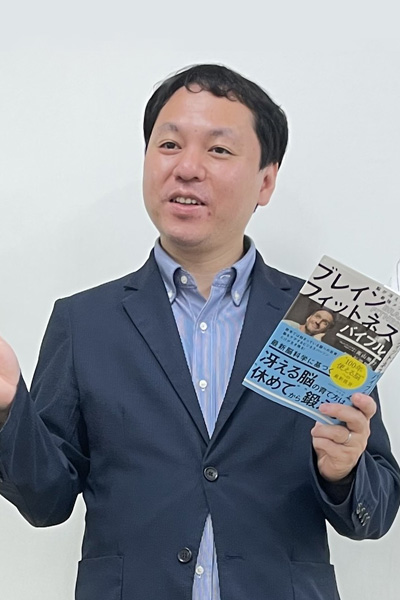誰もが安心して働ける環境づくりを 障がい者雇用にあたって押さえておきたい5つの注意点

アクセスランキング
これまで2回にわたり発達障がいをテーマに解説してきました。「発達障がいとは何か」、「大人の発達障がいとは」といった基礎的な内容から、精神疾患としての「症状」とは異なる、障がいゆえの「特性」についての理解、発達障がいの方への復職支援までを取り上げてきました。これらは、「障害者手帳」を所持していない方や、いわゆるグレーゾーンと呼ばれる方も含めた内容でした。
今回は、障害者手帳を所持して働く「障がい者雇用」について解説します。企業にとって障がい者雇用は、法令遵守だけでなく採用戦略や企業価値向上の観点からも重要性が増しています。また、近年は精神障がいや発達障がいなど、メンタルヘルスに関連する障がいがある方の雇用が増え、総務としても受け入れ環境や業務配分、日常的なサポート体制の整備が欠かせません。まずは制度や歴史といった基本的な知識から説明しましょう。制度を深く理解することは、安心して働ける職場づくりの第一歩です。
障がい者雇用と障害者雇用促進法について
障がい者雇用とは、障がいのある方が職場で力を発揮し、安定して働けるよう雇用することです。ここでいう「障がい」とは、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)を指し、それぞれの障害者手帳を所持していることが基本です。
障がい者雇用の歴史について簡単に紹介します。
1960年:身体障害者雇用促進法の成立(努力義務)
日本で初めて障がい者雇用に関する法制度が制定されましたが、当時は企業への「努力義務」にとどまりました。
1976年:法定雇用率の義務化
法定雇用率が努力義務から法的義務に強化され、一定の従業員数を雇用する企業に障がい者雇用が義務付けられました。当初は身体障がい者のみが対象でした。
1998年:対象障がい者の拡大
知的障がい者が対象に追加。2018年には精神障がい者も法定雇用率の対象となりました。
障害者雇用促進法は、障がいのある方の雇用を進め、安定した就労を支える法律です。企業に対して一定割合以上の雇用を義務付け、そのための支援制度や助成制度も整えています。
今でこそ障がい者雇用は広がっていますが、企業の意識を大きく変えたのは、制度改正と運用強化です。1976年の義務化に加え、1990年代後半から2000年代にかけて罰則や公表制度が整備されました。当初は従業員63人以上の企業が対象で、罰則は軽かったものの、「法律で定められた比率を守らなければならない」という意識が企業に芽生えるきっかけになりました。
その後、法定雇用率の引き上げや対象範囲拡大が進み、2000年代には障害者雇用納付金制度の運用が厳格化します。未達成企業には納付金(ペナルティー)、達成企業には調整金(インセンティブ)が支給される仕組みが定着し、「未達成はコスト負担になる」という認識が広がりました。これにより「単に雇用率を満たすだけでなく、定着をはかることが課題」という認識が広がり、企業における優先度が高まったと考えられます。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。