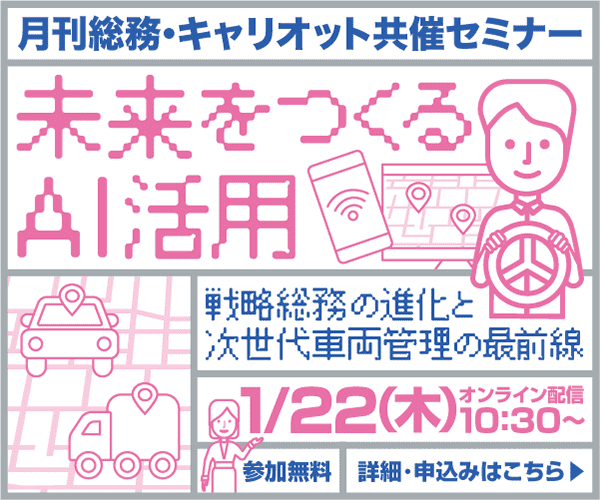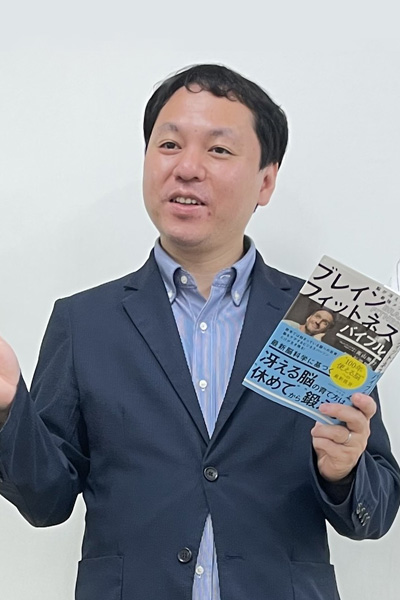周囲の誤解やハラスメントでメンタルヘルス不調に 発達障がいの「二次障害」への向き合い方

アクセスランキング
前回は休職者だけにとどまらず、働くビジネスパーソンの中でも課題として見受けられる「発達障がい」をテーマに解説しました。その中でも触れたように、大人になってから自身が発達障がいであると診断される人が増えています。特性に気付くことで対処の糸口が見えてくることもありますが、一方で、自分自身の特性に気付かないまま、「なぜうまくいかないのだろう」「なぜ自分はほかの人と違うのだろう」と、仕事や生活の中で悩みを抱えている方も少なくありません。
今回はそういった悩みから、発達障がいを主症状としながらも、続けて精神疾患に罹患してしまう「二次障害」と、そこから会社を休職された方への復職に向けて、本人、職場はどうあるべきかについて解説していきます。
発達障がいのグレーゾーンとは
発達障がいの「グレーゾーン」とは、医学的な診断基準には該当しないものの、日常生活や職場、学業などで一定の困難を抱えている状態を指します。
通常、発達障がいの特性は、以下の3つの段階があり、発達障がいのグレーゾーンは(2)の状態にあると考えられます。
(1)社会生活に支障を来す
(2)社会生活に支障を来す頻度が高い
(3)社会生活に支障を来す可能性がある
もう少し具体的に解説をしていくと、前回の記事で説明した発達障がいの種類である、自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)などの診断基準を全て満たすわけではないものの、その傾向や特性が見られる状態を指します。それにより、忘れ物が多い、人間関係がうまくいかない、こだわりが強い、感覚が敏感で疲れやすいなど、さまざまな場面で支障を感じることがあります。
しかし、診断が付かないことで公的な支援を受けられなかったり、障がいや病気と認識されず、周囲の理解に頼らざるを得なかったりすることが多いのが現状です。職場においては、グレーゾーンの方々が「努力不足」と誤解されることも多く、結果として強いストレスを感じ、メンタルヘルス不調を招くことがあります。これを二次障害と呼びます。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。