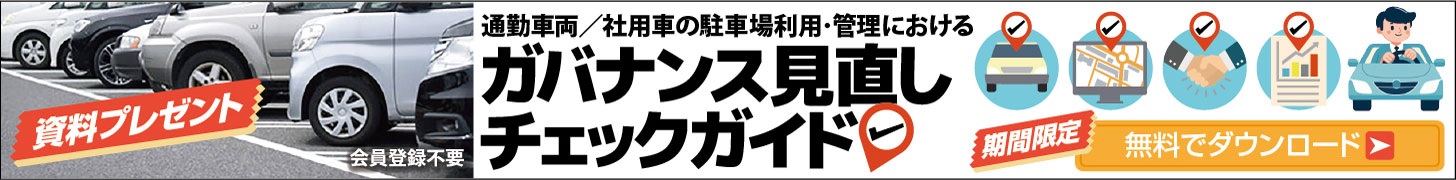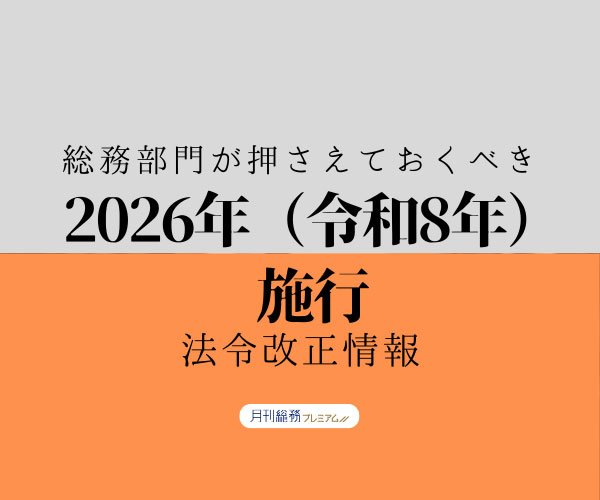119番通報で何を伝えるべき? 防火対策の基本と発災時の被害を最小限にする緊急対応手順

アクセスランキング
みなさんは「当社の防火対策と対応は万全です!」と自信を持っていえますか? 筆者はしばしば、中小企業を対象とした防災・BCPに関する講習会でレクチャーしたり、BCPの策定指導の一環として社内の防災点検に参加させていただくことがあります。そうした中で気付いたことは、防火対策は防災の基本中の基本でありながら、それほどしっかりとした対策が取られていないという現状でした。たとえば、「消火器の使い方を知らない」「消火器が更新されておらず、さびたボンベが倉庫の隅に転がっている」「防災訓練をやったことがない」「オフィスビルの合同避難訓練は、手の空いている社員がお付き合いで1人参加している」などとおっしゃる方が少なくないのです。そこで今回は、防災の基本に立ち返っていただくために、最も基礎的な「防火対策」と火災発生時の「緊急対応手順」についてお話しさせていただきます。
ポイント1:防火対策の基本
次の3つは火災を未然に防ぎ、発災時の人的・物的被害を最小限にとどめるための基本事項です。
(1)火気・危険物・火気設備の管理
建物の周囲や共用部に可燃性の物品が放置されていないか、ライターやマッチなどの火気類の適切な管理、喫煙場所の監視、コンセントのプラグのほこり、たこ足配線、カーテン、じゅうたんなどは防炎物品を使用しているかなど。
(2)消防用設備の管理
消火器や消火栓、スプリンクラ―、防火シャッター等の設置場所、それらの使用方法の理解、消防設備の操作に支障のある物が置かれていないか、適正に使用できるように管理されているか、消防設備の点検を行う有資格者の選任と所轄消防署長への報告、など。
(3)火災時の初動体制と避難管理
初期消火の正しい知識を身に付けているか、消防機関への通報を素早く行い、必要な情報を伝えられるか、避難経路を把握し適切に避難誘導が行えるか、など。避難の点検としては、廊下、通路、階段等に避難の支障となるものが置かれていないか、など。
ポイント2:緊急通報の一般的な手順
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。