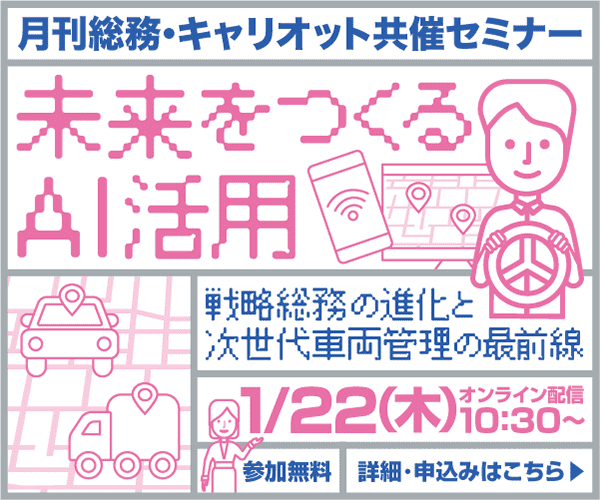生成AIで作られた著名人の詐欺広告に注意! 総務から始める「だまされない組織」のつくり方

アクセスランキング
近年、AI技術の進歩とともに、私たちの業務効率は飛躍的に高まりました。しかし、その一方で、悪意ある者たちもAIを活用し、より巧妙な詐欺行為を仕掛けてくるようになっています。その中でも、企業にじわじわと影響を与え始めているのが「生成AIを悪用した広告詐欺」です。一見すると、この問題は営業部門やマーケティング部門の課題と思われがちかもしれません。しかし、こうした詐欺への備えにおいては、情報統制やリスク管理を担う総務部門こそが重要な防波堤となるのです。本稿では、そうした広告詐欺の実態と、総務部門として企業と従業員を守るためにできる対策について、わかりやすく紹介します。
生成AIを悪用した広告詐欺とは?
生成AIなどの技術を用いて作成した偽の広告を、あたかも信頼できる広告のように見せかけてユーザーをだます手口です。SNSの広告欄やWebニュースの合間に、「◯◯社長が語る! 誰でももうかる投資法」といった見出しと、どこかで見たことのある著名人の顔写真が添えられている広告を目にしたことはありませんか。クリックしてみると、さもその人のインタビュー記事であるかのように見せかけたページが現れ、そこから怪しげな投資サイトに誘導される仕組みです。
海外では有名企業の創業者の顔と名前が勝手に使われ、仮想通貨関連の詐欺広告に利用された例があります。日本でも、大手メディアの名前を模した「偽メディアサイト」に掲載された広告を見た人が、数十万円以上の被害に遭ったケースが報告されています。企業の役職者がだまされ、会社の資金を詐欺グループに送金してしまうという、組織全体にかかわる重大な被害も起きています。
こうした詐欺は、従業員の個人端末や業務中のWeb閲覧を通じて忍び寄ってきます。一人が被害に遭えば、それは企業全体の信用問題にもつながりかねません。
なぜだまされてしまうのか?
このような広告は、一見しただけでは本物と見分けがつかないほど精巧に作り込まれています。最近では、偽のニュース番組風の動画、AIで合成された音声や表情を使った「フェイクインタビュー」までも登場しており、疑うことなくクリックしてしまうケースが相次いでいます。
また、詐欺に引っかかる理由は「不注意」や「知識不足」だけではありません。AI広告詐欺は、私たちの心理のスキを巧妙に突いてきます。広告には「急げ」「今すぐ」「あなただけに」といった「焦らせる言葉」が使われており、冷静な判断がしづらくなります。これは「権威への信頼」や「損をしたくない」という心理を巧みに突くテクニックであり、ITの専門家でさえだまされることがあるほどです。
総務部門ができる5つの対策
こうしたリスクに対し、総務部門はどのように備えるべきでしょうか。ここではすぐに実践できる5つのポイントを紹介します。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。