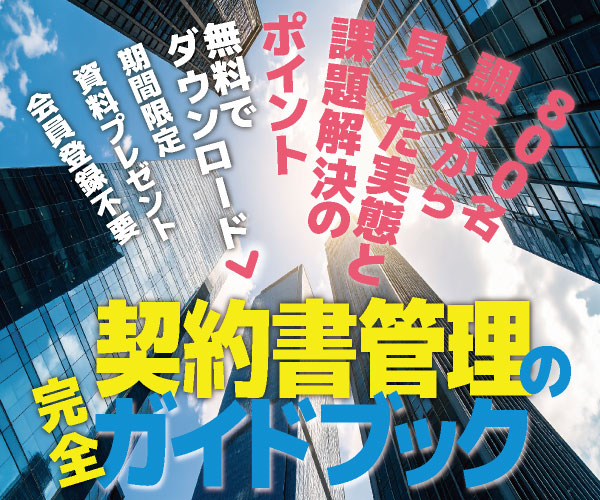総務の引き出し(採用)
採用活動の早期化の落とし穴にハマるな! 中小企業の作戦は「序盤を捨てる」or「M字で狙う」
株式会社人材研究所 代表取締役社長 曽和 利光
最終更新日:
2023年11月16日

アクセスランキング
コロナ禍もある程度過ぎ去ったこともあり、企業の採用意欲はさらに高まっています。リクルートワークス研究所によると、2024年卒の新卒採用求人倍率は1.71倍で、コロナ以前の水準に戻っています。学生が強く、企業が厳しい、いわゆる「売り手市場」になっています。採用が難しくなった企業は必死になり、結果、早期化が進んでいます。リクナビやマイナビなどのメガ就職ナビの正式オープンは政府の要請通り3月ですが、2024年卒では2月までにすでに半分の学生が面接を受けており、2割が内定を取得しているという状況です。さらに、選考解禁の6月時点では内定取得率は8割となっており、採用活動・就職活動の早期化は明らかになっています。
ときが過ぎれば就活生はどんどん減っていく
そうなると、「自社はいったいいつから採用活動を始めるべきなのだろう」という疑問がわいてきます。「みんなが早期化しているから、うちも早期化」でよいのでしょうか。むろん、早期化しなければ、どんどん市場から学生が減っていきます。
就職みらい研究所の「就職プロセス調査」を見ると、就職活動を続けている学生は3月時点で8割、4月で7割、5月で6割、7月で3割、8月で2割、9月では1.5割とどんどん減っていきます。普通に考えれば、たくさん学生がいる時期に採用活動をしなければ採れなくなってしまうと焦ることでしょう。
しかし、単純に早期化すればよいかというとそうでもありません。そこには落とし穴があります。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。