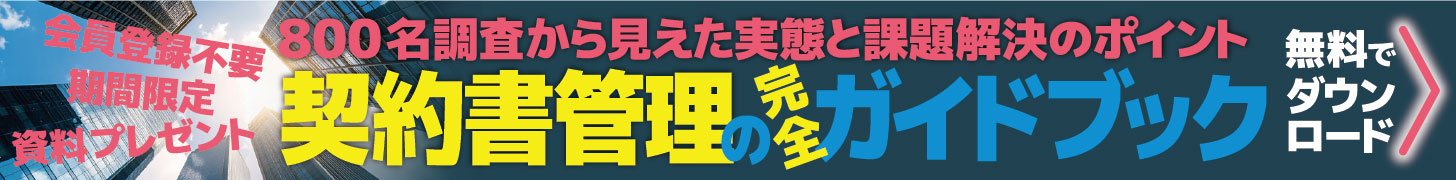自社をアピールするだけの構成ではダメ 企業も学生も有意義となるインターンシッププログラムとは

アクセスランキング
インターンシップの導入は、もはや新卒採用においては常識で、現在では多くの企業が当たり前のように実施しています。一方で、「果たして本当に採用に効果があるのか」「本選考につながるのか」と懐疑的な声も根強く存在しています。特に、夏季に行われるインターンシップについては、本採用活動までの期間が長いため、せっかく築いた学生との関係性が途中で途切れてしまうこともあります。その結果、「学生にとっては有意義だったかもしれないが、企業にとっては何か意味があったのだろうか」と感じるケースも少なくありません。
自社の魅力を伝えるよりも、学生に普遍的な学びを提供する方が効果的
もともとインターンシップは、学生がキャリアについて考えるきっかけを企業が提供するための取り組みですから、学生の役に立ったのであれば、一定の意義はあると考えることもできます。しかしながら、忙しい中で人員や予算という貴重なリソースを割いて行う以上、企業としてはブランディングや採用に対する効果を期待したくなるのは自然なことです。
効果的なインターンシップの設計をするには、「学生がどのようなことを知りたいのか」という視点が重要です。学生の多くは、必ずしも「その企業がどのような会社であるか」を知りたいとは考えていません。むしろ、自分のキャリアを考えるために役立つ情報や、仕事全般に対する理解を深めるような体験を求めています。
企業としては、自社の魅力を伝えたいという思いが先に立つかもしれませんが、それをいったん抑え、業界全体の構造や仕事の種類など、より普遍的な学びを提供する内容にすることで、学生の満足度は高まります。そうしたプログラムにすることで、学生にとっては学びが深まるだけでなく、企業にとっても、自社にまだ関心のなかった学生との接点を広げることができます。自社のことだけをアピールする構成にすると、すでに自社に興味を持っている学生しか集まらず、「何もしなくても受けてくれていた学生」との接点にしかなりません。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。