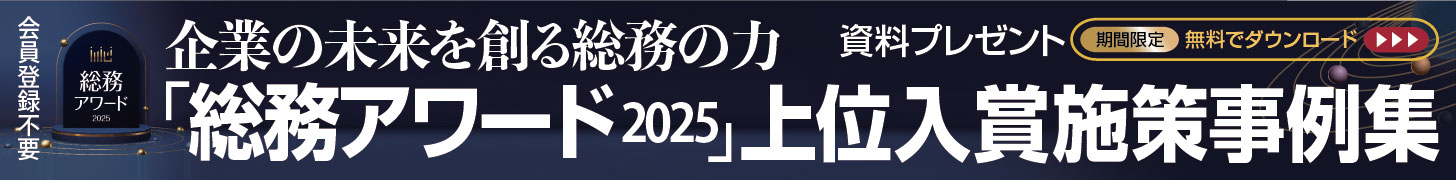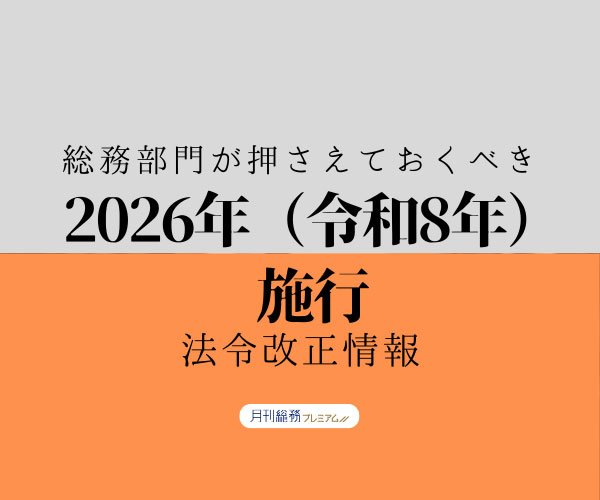今や環境問題にとどまらない経営の重要テーマに! 水が豊富なはずの日本に迫る「水リスク」とは

アクセスランキング
世界の水不足が深刻さを増す中、企業の水資源に対する責任がこれまで以上に問われています。水はあらゆる事業活動の土台でありながら、そのリスクは見えにくく、対策も後手に回りがちです。
日本は「水が豊かな国」という認識が根強い一方、実際には農産品など、多くの製品や原材料に「海外の水」を使っており、バーチャルウォーター(仮想水)の輸入大国でもあります。
今回は、水不足の国際的動向、日本企業のウォーターフットプリントの実態、そして水リスクに備えた戦略的アプローチと実践例を通じて、サステナブルな経営における「水」の重要性を考えてみたいと思います。
世界の水不足(Water Stress)は、企業活動にどのような影響をもたらすか?
国連の報告によれば、世界では約20億人の人々が安全に管理された飲料水を得られておらず、2030年までに淡水資源の不足は必要量の40%に達すると推計されています。気候変動による干ばつや洪水の頻発化に加え、人口増加と都市化の進行が、地球規模での水ストレスを加速させているのです。
この影響を直接受けるのが、水を大量に使用する産業、たとえば農業、紙・パルプ、化学、鉄鋼そして半導体などです。水不足は単なるコストに対する不安にとどまらず、サプライチェーンの断絶や地域社会との摩擦など、事業継続にかかわる重大なリスクをはらみます。
実際に、海外拠点を持つ企業の中には、地元住民との「水の利用権」を巡るトラブルに直面したケースもあります。これを受け、ESG評価機関や投資家は、水リスクの情報開示(例:CDP Water Security)を企業に強く求めるようになっています。
水リスクが経営に及ぼす影響
水不足は、工場の操業停止や生産遅延といった直接的なリスクにとどまらず、調達先の安定性や地域コミュニティーとの信頼関係、さらには企業ブランドや投資家評価にも直結しています。たとえば、水使用量の多い産業などでは渇水時の利用制限やコスト増加が経営を圧迫する可能性があります。さらに、気候変動の影響で「洪水と渇水が交互に発生する」現象も増えており、事業継続計画(BCP)の見直しが急務です。
以下は、企業経営における水リスクを、3つのレイヤーに整理したものです。
図表1 水リスクに関する本質の3つの区分
| リスク分類 | 内容 |
|---|---|
| (1)物理的リスク | 渇水・洪水・水質汚染など自然環境の変動が直接的に工場操業や物流に影響するリスク |
| (2)規制リスク | 各国の水利用規制や排水規制が厳格化される中、ライセンス取得や浄化コストが増加し、競争力に影響を及ぼすリスク |
| (3)レピュテーションリスク | 「地域の水を過剰に奪っている」「水資源保全に消極的」といった批判がSNSやメディアを通じて急速に拡散し、ブランドイメージが失墜するリスク |
日本は本当に「水が豊かな国」なのか?
日本は降水量が多く、上下水道インフラが整っていることから、「水に困らない国」というイメージが根強くあります。しかし、私たちの生活を支えている多くの製品は、農産品をはじめ、海外からの輸入品であふれています。つまり、こうした海外製品の生産には大量の水資源が使用されているのです。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。