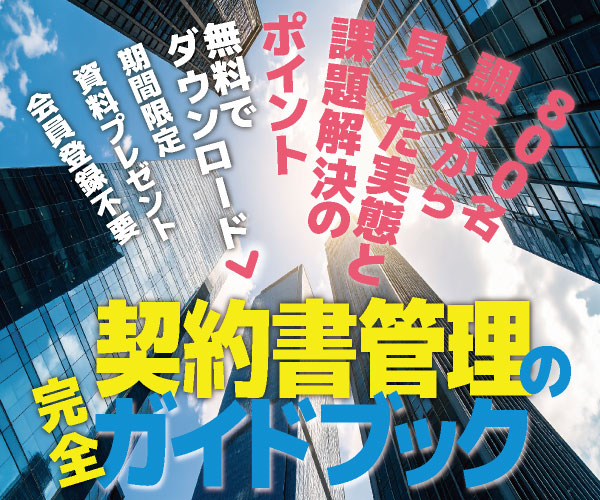目標が「女性管理職の比率を上げる」なら逆効果に ダイバーシティ経営を推進させる第一歩とは

アクセスランキング
今回は、第1回「『ダイバーシティ経営』実は中小企業にこそ大きな効果 成功につなげる7つのアクションとは」で紹介した、経産省のダイバーシティ導入ガイドライン「ダイバーシティ2.0」を基に、具体的な導入のステップをご紹介します。
ダイバーシティ経営において中途半端な取り組みは逆効果
第1回、第2回では、なぜ今ダイバーシティ経営が社会で問われているのか、SDGsとの関係性、また企業において導入するメリットなどについて説明しました。
ダイバーシティ経営は、より広い人材要件での採用が可能になることから「人材採用の成功」というメリットがあります。また多様な人材を企業に迎えることで「イノベーションの創出」、さらに個性を尊重する風土や仕組みの下、働きやすいと感じる社員が増え「社員定着率向上」が期待できます。
しかし、中途半端に取り組んだ場合、社員に混乱をもたらし、社員の時間を無駄に消費するだけで終わってしまうこともあります。ハレーションを起こして終わりだと逆に組織に不信感を覚える社員が増え、むしろ逆効果です。たとえば「女性管理職を何%に」など適当な数字だけを決め、人材要件を満たさない社員を管理職に据えた場合、部門全体の歯車がかみ合わず成果が落ちたり、周囲の目が厳しくなる、本人も過度なストレスを抱えるなど問題が起きる可能性があります。
以前、ある大手製造会社から管理職に昇格した女性社員の研修の依頼を受けました。総勢20人近くだったので、「この方たちはどのように選ばれたのですか?」と質問をしたところ、「評価の高い人から順番に選びました」という答えでした。政府が掲げる女性活躍推進の一環として、女性管理職を3割にする。そして、その結果を政府に報告する必要がありました。選抜された女性社員はみなさん戸惑いを隠せないようすでした。昇格とともに担当業務が変わることもなく、今日までサポート業務を中心に担ってきた人が、明日からみんなの上司となって仕事を進めなければならない。このような状況下で会社から業績アップを要求されても納得して働けるでしょうか?
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。