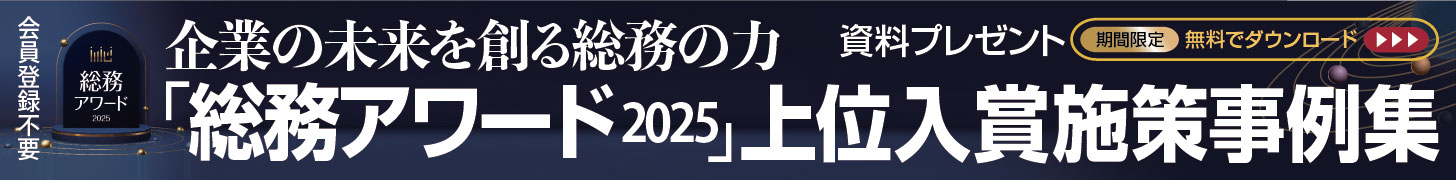「会社で初詣に行く」は人権問題になり得る? 総務担当者が考えておくべき「企業と宗教」

アクセスランキング
SDGsの実践には、全ての人の人権の尊重が切っても切り離せません。また、人権を尊重するということは、口先だけの意思表明ではなく、効果がある、具体的な行動が求められます。わが国のビジネスシーンではかつて「野球、宗教、政治の話はするな」といわれていましたが、信仰は人権問題、そしてこれまで考えてきたダイバーシティの問題にもかかわります。そこで、今回は企業が宗教とどのように向き合うべきか、について考えてみましょう。
積極的に語る人は少ないが、宗教人口の総数は約1億8000万人
宗教は古代から世界各地に存在し、社会の中核的価値観や心のよりどころとなり、人間の精神の在り方や行動に長く影響を与えてきました。歴史を振り返れば、宗教は庶民の暮らしと密接にかかわり、宗教がトリガーとなって歴史が動いたことは一度や二度ではありません。それだけ宗教は社会で大きな地位を占めていました。しかし、現代の日本社会では宗教について積極的に語る、という人は少数派でしょう。
一方で、日本社会には初詣やクリスマス、冠婚葬祭、宗教団体が運営する学校など、宗教的要素が多く存在しています。宗教行政を所掌する文化庁の令和4年版『宗教年鑑』では、日本の信者(宗教人口)の総数は約1億8000万人とされており、わが国の人口以上の宗教人口が存在するとされています。これは宗教団体ごとの信者のカウント方法が異なる、一人の信者が複数の宗教団体に所属していることなどが理由とされていますが、決して日本が無宗教社会ではないことを示すものといえるでしょう。そして、ビジネスでも商売繁盛や作業の安全を願い、あるいは祭礼などで寺社へ寄付をする、事務所に神棚を置いて祭る、社葬でお坊さんにお経をあげてもらうなど、儀礼的な形であっても、宗教とのかかわりは決して珍しいものではありません。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。