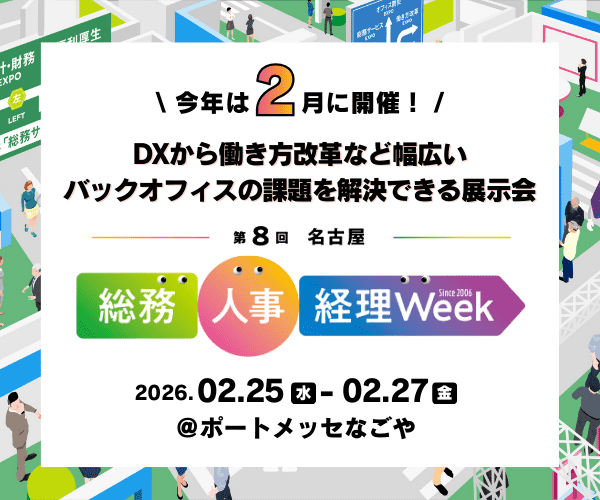アクセスランキング
今回は、企業と地域社会の連携の現状と課題について、導入のメリットとそのポイントを解説します。
変わりゆく企業と地域社会連携
地域社会との連携というと、お祭りやマラソンへの参加や寄付、清掃・美化などの奉仕活動を想起する人も多いのではないでしょうか。確かにこれまで地域と密な連携を取る企業といえば、地域密着型のビジネスモデルを持つ業種、店舗を構える小売業、地方銀行や信用金庫などの金融業、鉄道・バス・電力・ガスなどインフラ業などが多いイメージでした。たとえば銀行であれば、地域の発展がその店舗の利益にもつながりますし、地域住民を対象とする小売業やサービス業は、彼ら彼女らからの好感度が売り上げを左右し、自社の認知や信頼に直結するという認識で、地域へのCSR活動を行っていたように思います。
しかし、近年は「社会課題解決型」「官民連携」「エシカル消費(※)」といったキーワードや、この連載のテーマでもあるSDGs・サステナブル経営といった文脈で、今までのイメージとは大きく異なる地域社会連携が生み出されています。
※ 地域の活性化や雇用等を含む、人・社会・地域・環境に配慮した消費行動
たとえば、ソニー株式会社は子供たちの教育格差を減らすため、教育体験に恵まれにくい学童や子ども食堂にSTEM教育などを提供していますが、さらに2018年頃からは地方や離島などにもフォーカスした遠隔の無料授業を開始しました。愛知県では、環境や地域に配慮したエシカル消費推進に向けて、広く啓発し理解促進をはかり、持続可能な社会づくりにつながる消費者教育を進めています。このように、企業・自治体と地域との連携は地域密着型ではない業態やその地域に事業所を持たない企業にも広がり、多様な形を見せています。今回はそれらの事例やメリット・課題などをご紹介します。
地域連携の類型と近年のトレンド
企業が地域連携を行う例としては、以下のようなものがあります。
|
(1)地域イベントへの参加・協力 |
|
|---|---|
|
(2)環境保護・地域美化活動 |
|
|
(3)教育支援 |
|
|
(4)地域課題解決 |
|
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。